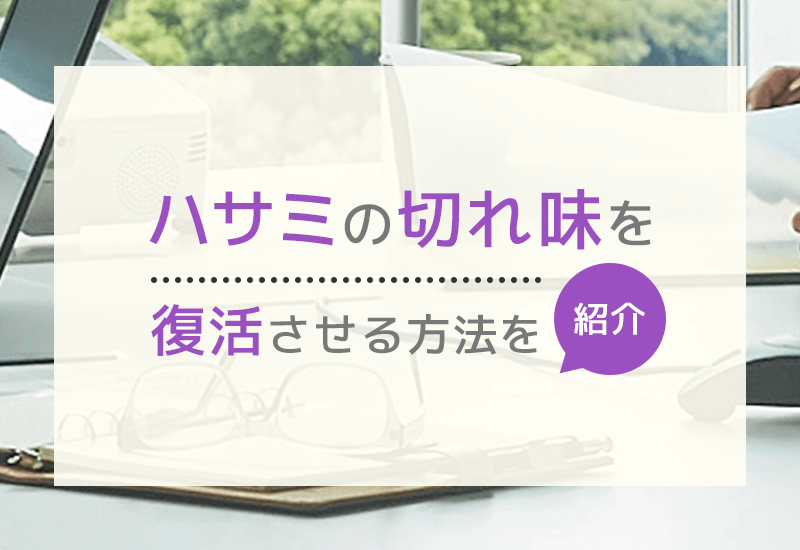
目次
ハサミを使おうとしたら切れ味が悪くて使えないという経験はありませんか。実はハサミは包丁のように研ぐことで、切れ味を復活させることが可能です。
このコラムでは、ハサミの研ぎ方や切れ味を復活させる方法などをご紹介します。
ハサミが切れなくなる理由
ハサミが切れなくなる原因は、主に「刃こぼれ」と「汚れの付着」の2つに分けられます。
ハサミは使用するたびに、摩擦で小さな刃こぼれが起きており、長い間使用しているとだんだんと切れ味が悪くなります。また、食べ物やテープなどを切ってそのままにしておくと、汚れや粘着剤が付着し切りづらくなります。
ハサミを研ぐ時の注意点
ハサミを研ぐときは研ぐ面に注意が必要です。「小刃(こば)」と呼ばれる刃の表面に角度が付いている所のみを研ぐようにしましょう。
ハサミは2枚の刃の噛み合わせを利用して切れるようになっています。そのため、刃の裏側も研いでしまうと2枚の刃が噛み合わなくなり、切れ味が悪くなったり使えなくなったりしてしまいます。
ハサミを研ぐ最適なタイミングは、小刃が摩擦などで傷付いて、細い線状の筋ができたときです。傷が深くなれば深く研がなければならないため、傷に気付いたときは早めに研ぐようにしましょう。
ハサミの正しい研ぎ方
ハサミの研ぎ方にはポイントがあります。間違った研ぎ方をしてしまうと、切れ味が悪くなってしまう場合があります。ハサミを研ぐときは怪我のないように注意して行いましょう。
準備するもの
ハサミを研ぐ時に準備するものは以下です。
・砥石
・ドライバー
・布
・液状研磨剤
・新聞紙
研ぎ方
研ぎ方を順番に説明します。ハサミの種類によっては簡単に分解できるものや自分で研ぐことが難しいものもあります。ハサミを研ぐ時は、取扱説明書を確認してから行うようにしましょう。
1.砥石を水につける
まずは砥石を水に浸します。砥石を水につけずに行うと摩擦が強く滑りが悪くなります。10〜15分ほど水に浸して砥石の色が変わるまでしっかりと水を含ませましょう。
2.ハサミを分解する
ネジで固定されているハサミの場合、ドライバーを使いネジを取って分解します。分解できないハサミは、できるだけ刃を大きく開きます。
3.サビや汚れを取る
ハサミを研ぐ前にサビや汚れをできるだけ落とします。サビや汚れは液状研磨剤で落とせます。布に適量を含ませてしっかりと磨き、磨き終わったら別の布でしっかりと拭き取りましょう。
4.ハサミを研ぐ
作業をするときは、砥石が滑らないように新聞紙などを下に敷いてから行いましょう。砥石にハサミの小刃の部分をあてて研いでいきます。
ハサミを研ぐときのポイントは3つです。
・角度に気を付ける
・力加減を均等にする
・とぎ汁を使う
ハサミを研ぐ角度としては、元々の刃の角度と同じくらいになるように意識しましょう。また研ぐときは、押すときと引くときの力加減が同じくらいになるように心がけます。力加減が同じくらいになることで刃の表面も均等になります。
力加減に大きな差が出てしまうと、切れにくくなる原因になるため注意しましょう。砥石が乾いてきたら水をかけて、出てきたとぎ汁を使ってさらにハサミを研いでいきます。とぎ汁には砥石の粒子が含まれているため、全体にまとわせながら研ぐことで研磨剤の役割を果たします。
5.すすぐ
研いだ後はきれいな水ですすぎ、布で拭き上げて乾燥させます。水分が残っているとサビの原因になるのでしっかりと乾かしましょう。
6.組み立てる
分解していた場合は、ドライバーを使いネジを締めて組み立てて完了です。組み立てたら切れ味を確認しましょう。
ハサミの切れ味を復活させる方法5選
砥石以外のものを使って、ハサミの切れ味を復活させる方法もあります。ハサミを研ぎたいけれど砥石がない、もっと簡単によく切れるようにしたいという方は、代用品での方法を参考にしてください。
汚れを取る
アルコールウェットティッシュなどを使い、ハサミの汚れを拭き取りましょう。頑固な粘着汚れには除光液をティッシュにつけて拭くと良いでしょう。汚れを拭き取るだけでも切れ味が良くなります。
アルコールウェットティッシュや除光液で拭いたあとは乾いた布で水分をしっかりとふき取り、サビを防ぎましょう。
アルミホイルを切る
折りたたんだアルミホイルをハサミでゆっくりと10回ほど切ります。アルミホイルの成分であるアルミニウムは、金属の中でもとても柔らかいため、融点(固体が液体になり始める温度)が低いのが特徴です。
ハサミで切るとアルミニウムが摩擦で溶け、ハサミの欠けた刃を補修して切れ味が良くなります。
紙やすりで研ぐ
紙やすりでハサミを研いで切れ味が復活する方法もあります。紙やすりを使う場合も小刃のみを研ぎます。紙やすりの目が粗いと傷がついてしまうため、できるだけ目が細かいものを選びましょう。
ドライバーを切る
ハサミでドライバーを切るようにして研ぐこともできます。ハサミの刃を大きく開き、ドライバーの鉄の部分にこすりつけることで切れ味が復活します。
ドライバーは表面がなめらかな、サビていないものを使用します。特に、硬くて頑丈なクロームメッキのドライバーがお薦めです。
固形石鹸をぬる
固形石鹸をハサミにぬることで石鹸の油分が刃につき、滑りが良くなります。また、石鹸をぬると刃についている汚れが落ちて切れ味が良くなります。
ハサミに石鹸を塗ることでサビ予防にもなりますが、食品用のハサミなど衛生品に使用するハサミに石鹸をぬることは避けましょう。
ハサミの切れ味を長持ちさせる方法
新しいハサミや研いだハサミの切れ味を長持ちさせるポイントは以下です。
・用途以外の使い方をしない
・汚れや水分を、そのままにしない
・湿った場所に保管しない
ポイントをおさえて、できるだけ長くハサミの切れ味を保ちましょう。1つずつ確認していきます。
用途以外の使い方をしない
ハサミは使う用途によって、刃の作りが異なります。
例えば、布用のハサミは柔らかい布を切るために作られているので、紙を切るハサミよりも刃が鋭く薄い作りになっています。そのため布よりも硬い紙を切ってしまうと刃が傷みやすくなります。
ハサミは紙用、布用、食品用など用途によって使い分け、用途以外では使わないようにしましょう。
ハサミの種類について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。
ハサミの効果的な選び方とは?種類や正しい使い方まで徹底解説!
汚れや水分をそのままにしない
ハサミを使った後、汚れや水分が付いていたらアルコールウエットティッシュなどで汚れを拭き取り、乾いた布で水分をしっかりとふき取りましょう。また、サビを見つけたときは液状研磨剤などを使いできるだけ早めにサビを取るようにします。
汚れや水分はサビや切れ味が悪くなる原因になり、ハサミの刃が欠けやすくなります。
湿った場所に保管しない
ハサミを湿った場所に保管するとサビの原因になります。風通しの良い涼しい場所に保管して、サビを防ぎましょう。
【番外編】ハサミの安全な捨て方
ハサミは不燃ごみや危険ゴミとして分別する地域が多いですが、普通ゴミとして出せる所もあるため自治体のWebサイトなどを確認して指定の日に捨てるようにしましょう。
ハサミを捨てるときは、刃をダンボールや新聞、厚紙などで包み、ガムテープで巻きつけて抜け落ちないようにします。ゴミ袋に入れたら目立つところに「キケン」などと注意書きをします。
ハサミをそのまま捨てると作業員の方の怪我に繋がり危険です。捨てるときはしっかりとマナーを守りましょう。
まとめ
ハサミの研ぎ方と切れ味の復活方法をご紹介しました。
ハサミも包丁のように研ぐことで、簡単に切れ味を復活させることができます。ぜひ実践してみてはいかがでしょうか。
使用方法や保管方法にも気を付けて、切れ味を長く保てるようにしましょう。
用途別のハサミがほしい、ハサミを研ぐために砥石が欲しいと思ったら「スマートオフィス」がお薦めです。たくさんの種類から選ぶことができ、オフィス用品購入に関するお悩みを相談することもできます。
ぜひスマートオフィスをご検討ください。
