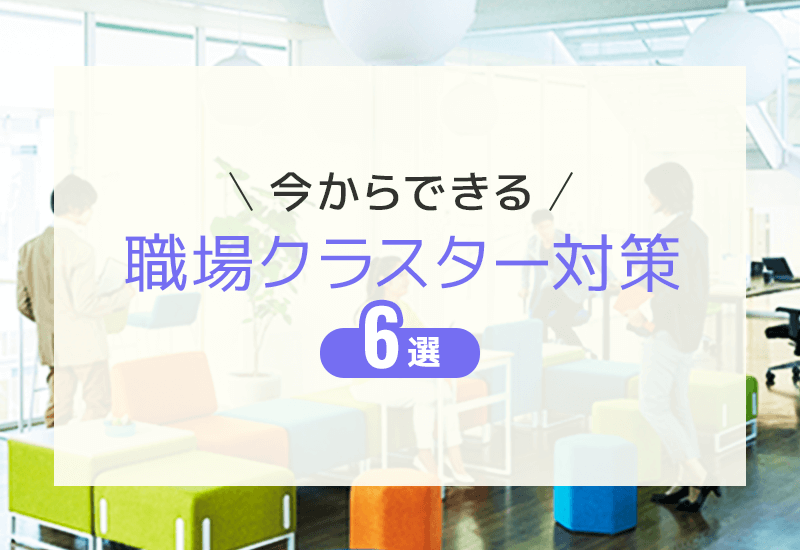
目次
新型コロナウイルスやインフルエンザなど、感染力の高いウイルスの流行で「クラスター」という言葉を耳にするようになりました。職場クラスターにおける感染対策は、事業者の自主的な判断と取組が基本です。今後、新たな感染症が流行・拡大し、クラスターが発生しないとも限らないため、対策を講じていく必要があります。
本コラムでは職場クラスターの定義をはじめ、職場クラスター発生によるリスク、押さえておきたい対策について詳しくご紹介いたします。
職場クラスターの定義
クラスターとは「群れ」「集団」を指す言葉で、一定数以上の人が特定疾患にり患している状態を指します。元々は、化学や数学、IT領域において使われていた言葉で、分子等が結合したり、システムを一つに統合したりといった状態をクラスターと呼びます。
感染症においては「小規模での集団感染」や「特定の感染疾患が集まった状態」といった患者の集団を指し、集団でり患するといった意味合いで使われることが多いでしょう。
職場におけるクラスターは何人ぐらいからが該当するのか?と気になる方もいらっしゃるでしょう。厚生労働省の定義によると、「集団発生とは、当面の間接触歴等が明らかとなる5人程度の発生を目安とする」とされています。
会社に職場クラスターの発生責任はあるのか?
職場でクラスターが発生した場合、懸念すべきは安全配慮義務をクリアしているかどうかという点です。
安全配慮義務とは、従業員を雇用する側である使用者が、労働者の心身と健康を守るために配慮すべき義務を指します。職場でクラスターが発生した場合であれば、従業員が感染しないように「密」を避ける環境を作っていたのか、定期的な換気を行っていたか、といった事柄が問われることになります。
会社の感染対策不足によって感染したといった場合、訴訟のリスクもあり得るので注意しましょう。
職場クラスターのリスク要因
このように訴訟のリスクもある職場クラスターは、企業としても避けたいところです。それでは、どのような場所において職場でのクラスターは発生するのでしょうか?具体的な場所やシーンをご紹介いたします。
3密の環境
職場におけるクラスターは、三密(密閉空間、密集場所、密接場面)で起こると言われています。職場であれば、話をするところ、食べるところ、集まるところが該当します。また、大きな声を出さなければ話ができない場所は、飛沫感染リスクが高くなります。
<具体的な場所やシーン>
・職場でのミーティング
・接待を伴う飲食店
実際、多くの人が一度に感染するクラスターは、これらの場所で起こっていることが多く、気を付けたいところです。
基本の感染症対策不足
飛沫感染を防ぐためには、定期的な換気をはじめ、人と人との距離を保つことや、多くの人が集まらない環境づくりが重要です。このような日常的な感染対策が、職場でのクラスターを防ぐことに繋がると言えます。一方、基本的な感染症対策が行われていない職場においては、クラスターが起こるリスクは高くなると言えるでしょう。
押さえておくべき基本の職場クラスター対策6選
多くの人が集まる職場において、感染しないようにリスクヘッジを行うことはもちろん、感染した従業員への対応を理解しておくことは非常に重要です。
ここでは、このような職場クラスターのリスクを低下させる際に有効な職場のクラスター対策を厳選して6つご紹介します。
基本の感染症対策を徹底する
集団で感染症にかからないためには、基本的な感染症対策が有効です。感染予防には、ソーシャルディスタンス、マスクの着用や手洗い、換気の実施といった、従業員による協力も欠かないでしょう。
また、企業側の対応として、こまめなドアノブの消毒、消毒用アルコールの常備、在宅勤務や時差通勤といった勤務体系の導入など、職場の状況に応じた対策が求められます。在宅勤務・テレワークを実施する際には、特にメンタルヘルスについても留意しつつ、職場状況に応じて対策を講じましょう。
クラスター発生後の流れを決めておく
職場でのクラスター発生は、企業イメージを悪化させることにも繋がりかねないため、可能な限り避けたいものです。しかし、万が一不足の事態が起こってしまった場合を想定し、どのような流れで対応を行うべきなのかを決めておくことは非常に重要です。
例えば、発生場所が企業のオフィスビル内なのか、店舗や工場なのかによっても、接触相手の数が変わるため対応は異なるでしょう。接触相手が従業員同士だったのか、不特定多数を含むかどうかによっても、対応する事柄が変わってきます。
まずは自社の状況に応じて、職場でクラスターが発生した際は、誰が指揮をとって現場を仕切るのかをはじめ、クラスター発生後の流れについてもあらかじめ決めておくことが重要です。
<決めておきたい事柄>
・クラスター発生時に報告する人
・接触者のリストを作成する人
・クラスター発生後の働き方
・取引先や社内への情報共有
・欠勤者のカバー
・社内の消毒・清掃
連絡が必要な場所を把握しておく
職場でクラスターが発生した場合、保健所や帰国者・接触者相談センターへの連絡が必要となります。厚生労働省の「保健所管轄区域案内」から全国にある保健所の連絡先や住所が確認できますので、事前にチェックしておくと良いでしょう。
また、クラスターが発生した場所が店舗だった場合であれば、お客様への連絡が必要となるでしょう。工場であれば、取引先なども報告対象となるかもしれません。どこまでを報告対象とするのか事前に決めておき、連絡先を控えておくとスムーズでしょう。
感染者の休業指示や賃金を決めておく
職場で感染者が出てしまった場合、感染者への休業を誰が申し伝えるのか?期間はどの程度とするのか、といった事柄は決めておきましょう。企業側は休業期間中に休業手当を支払う義務は法律上ありませんが、従業員が生活に困窮しないよう有給休暇を推奨するなど、声掛けを忘れないようにしましょう。
また、職場で新型コロナウイルスに感染した場合は、労災保険給付の対象となります。人と接する機会の多い職場など、感染経路が職場かどうか不確定な場合でも労災認定されているケースが多いため、基本的には下記のような手当を貰えると認識しておきましょう。
<労災認定されると支給される手当>
・療養補償給付:原則として無料で治療を受けられる
・休業補償給付:療養のため仕事を休み、給与を受け取っていない場合、給付される手当
・遺族補償給付:業務で感染して亡くなった場合、家族が貰える手当
社内清掃と消毒を行う
職場でクラスターが発生した場合、保健所からクラスターが発生した場所の消毒を行うように指示されます。
しかし、消毒する場所に応じた濃度の消毒液を準備する必要があるため、「自分たちできちんと消毒できているか不安…」「感染が怖いので、できれば専門業者に委託したい」という方も多いのではないでしょうか。このような場合であれば、都道府県別に専門の消毒業者が存在しますので、相談すると良いでしょう。
補助金や助成金を調べておく
新型コロナウイルス感染症の影響により休業を余儀なくされた場合、休業する事業者に対して休業手当の一部を助成する制度があります。都道府県ごとに制度が異なるため、事業所の場所に応じて確認しておくと良いでしょう。
・雇用調整助成金:事業主が労働者に休業手当を支払う場合、一部が助成される制度
・小規模事業者持続化補助金:持続的な経営に向けた経営計画に基づき、経費の一部を補助する仕組み
職場クラスター対策をより効果的にするために
職場におけるクラスターを想定し、事前に対応フローや連絡先を確認しておくことは非常に重要です。また、このような事前準備が、職場でクラスターが発生した際の対策をより効果的にすると言っても過言ではありません。具体的な内容をご紹介します。
感染対策のシミュレーション
そもそも、なぜ感染症は拡がってしまうのでしょうか。感染症は「病原体」「感染経路」「宿主」の3つの要素が揃うことで、感染が成立すると言われています。そのため、これら一つひとつをしっかりと対策し、抜け漏れがないかの確認が重要です。
普段から対策フローを確認・練習してシミュレーションしておくことで、抜け漏れがないかを確認できます。そのため、感染経路を含めたシミュレーションを行っておきましょう。
特に、感染経路については、さまざまな経路が想定されるため、既知の内容から新たな対策を講じる必要性を感じることができるので、ぜひ見直しをお薦めします。
従業員を心理的にサポートする
新型コロナウイルスの感染拡大によって、これまで感じたことのない不安や焦りに襲われるという人も少なくありません。例えば、職場でクラスターが発生した場合は、これまでの生活が一変するため、丁寧なサポートが必要だと言えます。
このような認識を従業員全体が持つよう注意喚起を行うだけでなく、感染した従業員に対しては定期的に連絡を取る、定期的な病状の確認、声掛けといった事柄を心掛けると良いでしょう。
まとめ
職場でのクラスターは、従業員だけでなく事業主の負荷を伴うものです。そもそも発生しないように普段から心掛けるだけでなく、日々の対策も怠らないようにしましょう。
このような職場のクラスター対策において、空気清浄機や加湿器、サーキュレーター、検温器といった機器の購入を検討される方もいらっしゃるでしょう。
法人向けオフィス通販スマートオフィスには、クラスター対策になるさまざまな商品を取り揃えています。豊富な商品を取り揃えるとともに、オフィス用品購入に関する悩みを相談することもできます。ぜひご活用ください。
