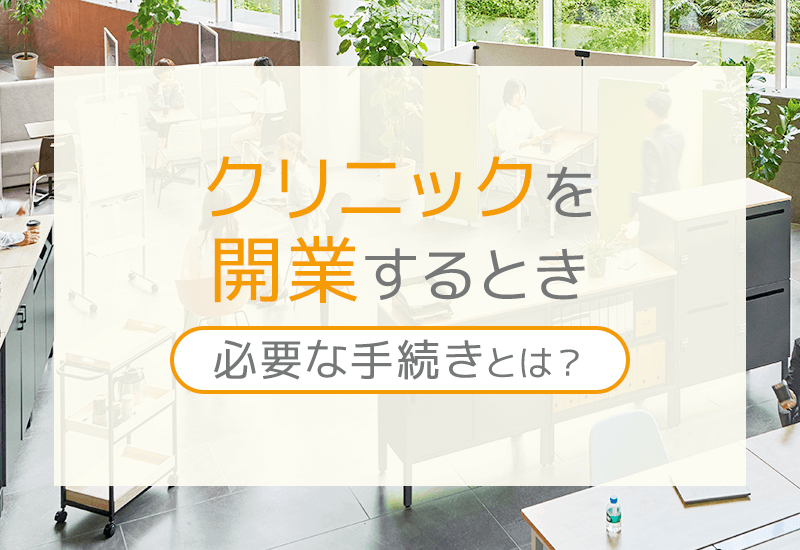
目次
クリニックの開業には、さまざまな手続きや準備が必要です。あらかじめ開業の流れを把握し、しっかりとした計画を立てることが、スムーズな開業の実現に繋がります。
クリニックの開業を決めたものの、「どのような手続きや準備が必要なのだろう」と悩む方は多いのではないでしょうか。
このコラムでは、クリニック開業に必要な手続きやスケジュール、内装工事で気をつけるべきポイントについて解説します。
クリニック開業の主なスケジュール
クリニック開業の準備は、一般的に1年〜1年半ほど前から始めます。開業までにするべきことは多岐にわたるため、段取りよく準備を進めなくてはなりません。
ここでは、クリニック開業の準備の主なスケジュールを紹介します。いつ、何をすべきなのか、クリニック開業までの流れを掴みましょう。
13〜18ヶ月前
クリニック開業にあたり、はじめに取り組むべきことは以下です。
・経営理念や診療方針を決める
・開業までのスケジュールを立てる
・事業計画の策定
一つずつ詳しくみていきましょう。どの項目も開業準備の基盤となる重要な要素となるため、きちんと練り上げることが大切です。
経営理念や診療方針を決める
まずは、クリニック開業の目的や方向性を示す重要な指針となる経営理念、診療方針を策定します。
経営理念とは、何のためにクリニックを開業したのか、目的や存在意義を明確に示すものです。診療方針とは、地域医療の中で目指すべきポジションを示すものです。
経営理念や診療方針の策定は、クリニックの開業準備に必要なだけでなく、開業後の経営の土台にもなるため、時間をかけて慎重に考える必要があります。
開業までのスケジュールを立てる
開業予定日から逆算し、具体的なスケジュールを立てます。ただし、緻密なスケジュールを立てたとしても、必ずしもその通りに進むとは限りません。想定外のトラブルが発生し、作業が遅れることもあるでしょう。
トラブルによって作業が遅れた場合、その後の作業にも影響を与えます。予定が後ろ倒しとなった際には、開業予定日までに準備が間に合わない可能性もあります。万が一に備え、余裕をもったスケジュールを立てましょう。
事業計画の策定
事業計画とは、クリニックの開業を成功に導くための計画です。クリニックの開業に必要な資金をどのように調達するか、開業後にはどのくらいの利益が見込めるかなどの計画を策定します。
曖昧な事業計画では、開業後の資金繰りや資金調達に苦労し、経営が悪化する恐れがあります。安定した経営を実現するためにも、現実的で無理のない事業計画を策定しましょう。
7〜12ヶ月前
開業予定日の7〜12ヶ月前にやるべきことは以下です。
・土地選び・物件の選定
・資金調達
資金が調達できなければ物件の契約ができないため、土地や物件の選定と資金調達は同時進行できるとよいでしょう。
土地選び・物件の選定
クリニックを開業する土地および物件の選定は、経営の成功を大きく左右します。通院のしやすさや地域の人口構成、競合クリニックの有無などをチェックし、慎重に選定します。
良い物件が見つかったとしても、あまりに高額な家賃の場合は、経営を圧迫する要因になりかねません。事業規模に見合った家賃なのか、その家賃に見合った来院数は見込めるのかなども考慮しましょう。
資金調達
クリニックの開業には、物件の契約や内装工事費、医療機器の初期投資など、多くの費用が必要です。その費用を自己資金で補えない場合は、助成金や金融機関の融資などを受け、資金を調達しなければなりません。
金融機関によって異なりますが、融資を受ける際には審査があります。申し込みをしてすぐに融資が受けられるとは限らないため、開業後の運転資金の確保も視野に入れ、 余裕をもった資金を調達しておくと安心です。
4〜6ヶ月前
開業予定日の4〜6ヶ月前にやるべきことは以下です。
・内装工事
・医療機器の選定
物件を決め、不動産契約を交わしたら、いよいよ内装工事に取りかかります。内装工事は導入する医療機器の寸法を考慮した上で進めましょう。
内装工事
経営理念や診療方針を基に、内装工事に着手します。賃貸物件の場合、オーナーや管理会社に、どのような内装工事が行えるのかを確認しておく必要があります。
クリニックの内装工事では、医療法や建築基準法、消防法などの法律を遵守する必要があることも覚えておきましょう。
内装工事には、設計費や材料費、設備工事費など、多くの費用がかかります。費用を抑える方法として、複数の内装工事業者に相見積もりをとったり、医療用品を扱うオフィス通販を併用したりなどが有効です。
医療機器の選定
クリニックの診察内容に見合った医療機器を選定します。開業日までに必要な医療機器を導入できなければ、クリニックは開業できません。医療機器の選定をするとともに、必ず納期の確認も必要です。
大型の医療機器は前もって準備していても、体温計や血圧計といった小型の医療機器は忘れがちです。準備し忘れがないよう、必要な医療機器のリストを作っておくとよいでしょう。
1〜3ヶ月前
開業予定日の1〜3ヶ月前にやるべきことは以下です。
・税理士・公認会計士・社労士の選定
・スタッフの採用・研修
・ホームページの作成
スムーズな開業を実現するために、スタッフの採用やクリニックのホームページの作成を行います。
税理士・公認会計士・社労士の選定
クリニックの運営によって得た利益は事業所得となるため、納税の義務があります。必ず確定申告をし、税金を納めなければなりません。
申告をし忘れていたり、申告が漏れていたりした場合には、加算税や延滞税などの追徴課税が課せられます。正しく納税するためにも、税理士や公認会計士といった専門家のサポートを受けることをお薦めします。
従業員数が多い場合は、労働・社会保険のエキスパートである社労士との契約も検討するとよいでしょう。
スタッフの採用・研修
クリニックの開業には、受付業務や診療をサポートしてくれるスタッフが必要です。どのような人材が必要なのか、条件を明確にし、募集および採用面接を行います。
開業前にはスタッフの研修も必要です。経営理念や診察方針の共有やシステム操作、マナーなど、さまざまな研修を行い、開業に備えましょう。
研修は、スタッフ同士のコミュニケーション活性化にも繋がります。スタッフ同士の連携がとれていると、スムーズな診察が可能となり、患者の満足度向上も期待できます。
ホームページの作成
開業当初はクリニックの認知度が低く、集患に苦戦しがちです。認知度を上げ、来院数を増やすためにも、クリニックのホームページを作成しましょう。開業前に宣伝活動を行うためにも、開業日の1〜3ヶ月前にホームページを公開するのが理想的です。
ホームページの作成は、重要な集客方法の一つです。経営戦略やマーケティングのノウハウがある、広告代理店や制作業者などに作成を依頼し、ホームページを効果的に活用するとよいでしょう。
〜1ヶ月前
準備も終盤となった開業予定日1ヶ月前には、行政への届出や手続きを行います。開業前の慌ただしい時期は、ミスや手続き漏れが発生しがちです。手続きが遅れると開業日に開業ができない恐れもあるため、念入りな準備が必要です。
必要書類の準備・行政等への届出
クリニック開業する際には、保健所に「診療所開設届」の提出が必須です。開業する地域を管轄する厚生局には、保険医療を実施するための「保険医療機関指定申請書」を提出します。
さらに、個人で事業を開始する場合は、税務署に「開業届」、各都道府県税事務所に「個人事業開始申告書」を届け出なければいけません。その他にも、診療科目や使用する医療機器に必要な届出が数多くあります。
提出先や提出期限、添付書類などの詳細は、それぞれ異なります。届け漏れのないよう、必ず事前に各機関に確認したうえで準備をしましょう。
クリニック開業のポイント
クリニックをスムーズに開業するためには、押さえておくべきポイントが3つあります。
・診療圏調査を行う
・医師会に挨拶・入会する
・開業支援サービスを活用する
一つずつ解説します。
診療圏調査を行う
クリニックを開業する土地を選定する際には、診療圏調査を行いましょう。
診療圏調査とは、開業予定地周辺の状況を調べ、対象となる患者数が1日あたりどのくらい見込めるのかを把握するものです。 算出された数値が大きいほどニーズが高く、クリニックの開業に適した土地であることがわかります。
ただし、診療圏調査の結果は、あくまでも目安です。診療圏調査の結果のみに頼るのではなく、実際に現地へ足を運び、自分の目でも確かめることも大切です。
医師会に挨拶・入会する
日本医師会とは、医師の生涯研修や地域医療の推進発展など、さまざまな活動を行う団体です。医師であれば誰でも日本医師会への入会ができますが、義務ではありません。
しかし、入会することで検診や予防接種の受託が可能になったり、医療業界の情報を入手しやすくなったりといったメリットが得られます。
地域医療を行うためには、周辺の医療機関とのコミュニケーションが欠かせません。医師会に入会するしないにかかわらず、開業が決まった早い段階で挨拶をし、良好な関係を築いておくことをお薦めします。
開業支援サービスを活用する
クリニック開業には多くの手続きが必要となり、遵守しなければならない法律も数多くあります。スムーズな開業をするためには、クリニック開業に関する知識と実績をもった開業支援サービスや開業コンサルタントを活用するとよいでしょう。
開業までの手続きだけでなく、開業後のサポートも受けられるため、安定したクリニック経営が目指せます。
自己資金を準備しておく
クリニック開業に準備しておく自己資金は、開業資金の1〜2割程度が目安です。自己資金が少ないからといって、開業ができないわけではありません。自己資金が少ない場合は、金融機関から融資を受けることでクリニックを開業できます。
ただし、自己資金の有無を融資の審査基準としている金融機関もあります。融資を検討している場合でも、ある程度の自己資金を準備しておきましょう。
クリニックの内装工事で気をつけるべきポイント
クリニックの内装は、来院者に「また来院したい」と思ってもらえるような、清潔感や安心感のある空間を演出することが大切です。
では、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。クリニックの内装工事で気をつけるべきポイントを紹介します。
デザインのコンセプトを決める
内装デザインの方向性やテーマを明確にするために、デザインのコンセプトを決めます。デザインのコンセプトは、「なぜクリニックを開業したのか」「どんなクリニックにしたいのか」など、経営理念や診察方針をベースにします。
デザインのコンセプトを決めないまま内装工事を進めると、一貫性がない居心地の悪いクリニックになりかねません。デザインのコンセプトは、内装工事業者と共有し、施工とズレが生じないようにします。
また、内装デザインに合う、備品の選定も重要です。あらかじめ、 医療関係の備品を扱う通販サイトやカタログをチェックしておくと、備品の選定もスムーズになります。
患者動線を確保する
クリニックの内装工事では、患者さんの快適な環境をつくるための動線確保が必要です。患者動線は、受付、待合室、診察室、トイレなど、患者さんのスムーズな移動を意識します。患者動線が確保された院内は、患者さんの利便性が向上し、居心地の良さに繋がります。
患者動線は、開業後も定期的な見直しが必要です。患者動線の見直しに合わせてレイアウト変更ができるよう、待合室や診察室に置く椅子やテーブルは、簡単に移動できるものがお薦めです。
防音対策を行う
患者が医師や医療スタッフと交わす会話には、診療内容や病状といったプライベートな内容が含まれます。そのため、診察室を中心に、会話が他の患者に聞こえにくいレイアウトにしたり、防音遮音の内装工事を行ったりなどの防音対策が必要です。
クリニック内の防音対策には、防音工事をする他、パーティションを設置するのも有効です。細菌の増殖を抑制する抗菌タイプのパーティションは、クリニックでも安心して使用できます。
ユニバーサルデザインを取り入れる
ユニバーサルデザインとは、性別や年齢、国籍や障がいの有無などにかかわらず、誰もが使用しやすいデザインを指します。
クリニックの内装で取り入れるユニバーサルデザインとは、わかりやすい案内看板や患者動線に添った手すりなどです。車いす利用者のために十分な通路幅を確保したり、受付カウンターを低くしたりなども、ユニバーサルデザインを取り入れた事例です。
ユニバーサルデザインを意識した内装は、患者さんの利便性が向上するだけでなく、医師やスタッフが従事しやすい環境づくりにも繋がります。
まとめ
クリニックを開業するには、経営理念の策定や物件の選定、内装工事など、やるべきことが数多くあり、スケジュール管理や事前準備が欠かせません。
クリニック開業のポイントや内装工事で気をつけるべきことを、あらかじめ確認しておくと、スムーズな開業が可能です。
期限が限られている開業準備は、さまざまな作業を並行して進める必要があります。開業支援サービスや開業コンサルタントを活用し、開業準備の効率化を図りましょう。
クリニックの開業準備の効率化には、法人向けオフィス通販サイト「スマートオフィス」の利用がお薦めです。スマートオフィスでは、クリニックの開業に必要な物品(間接資材)を取り揃えるとともに、購入に関する悩みを相談できるサービスも提供しております。ぜひ、ご活用ください。
