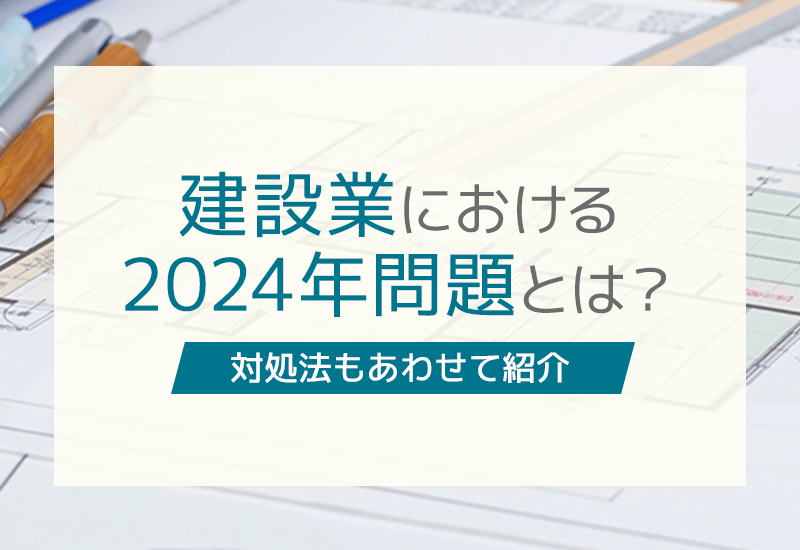
目次
2024年4月から、建設業でも「働き方改革関連法」(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)の時間外労働上限規制が適用となります。
この規制を受けて、建設業では「2024年問題」と呼ばれる問題が懸念されており、働き方改革の推進とそれに伴う労働環境の整備が、急速に求められるようになりました。
このコラムでは、時間外労働上限規制によって引き起こされる問題や人手不足など、「建設業の2024年問題」について解説し、その対処法をご紹介します。
建設業の2024年問題とは
2019年4月1日施行の「働き方改革関連法」により、時間外労働の上限規制が適用(中小企業では2020年4月より順次適用)となりましたが、建設業や運送業など一部の業界では、5年間の猶予期間が設けられていました。
その猶予期間が終了する2024年4月1日以降は、建設業も適用対象となり、時間外労働時間が原則「月45時間・年360時間」に制限されます。
「建設業の2024年問題」とは、これまで長時間労働が常態化していた建設業界において、労働時間の制限によって生じることが予想される、労働力不足などの問題の総称です。
では、2024年4月から、建設業の労働時間規制はどのように変わるのでしょうか。規制内容や罰則について、詳しく見ていきましょう。
時間外労働の上限が規制される
2024年4月から、建設業においても時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として「月45時間・年360時間」となります。
労働基準法では、法定労働時間を原則「1日8時間・週40時間以内」としており、これを超過した分が時間外労働に該当します。
臨時的な特別の事情があって労働者と使用者が合意した場合は、特別条項が適用され、例外として年720時間(月平均60時間)以内であれば時間外労働が可能です。
しかし、その場合も、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満とし、その平均を2か月~6か月のすべてにおいて月80時間以内としなければなりません。さらに、時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月までとされています。
ただし、災害からの復旧・復興のための事業では、特例として「時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満・2〜6か月の平均は80時間以内」は適用されません。
違反すると罰則が科せられる
上記のような労働時間の上限規制に違反すると、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が科せられることがあります。
また、規制を大幅に超える時間外労働をさせた場合など、悪質なケースでは、厚生労働省から企業名を公表される可能性があるので注意が必要です。
建設業が5年間も時間外労働上限規制を猶予された理由
先述のとおり、大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から「働き方改革関連法」が順次適用となっていました。
そのような中、建設業で5年間も適用が猶予されていた背景には、工期を遵守する業界特有の事情や人手不足の影響で、長時間労働が常態化していたという業界の労働環境の問題があります。
これらの問題は短期間では解決が難しいため、同じような労働問題を抱える運送業とともに、5年間の猶予が与えられていました。
時間外労働時間の上限により懸念される問題点
時間外労働時間を制限することは、労働者の健康障害を防ぐという観点でとても重要なことです。
しかし、建設業界においては、この上限規制によって懸念される問題も少なくありません。まず、一人あたりの作業時間が短くなってしまうことが挙げられます。
その結果、これまでより工期が長くなってしまうため、受注できる案件数も減り、企業の減益にも繋がる可能性があるのです。
また、労働者にとっても、残業代を含めた給料の減額が懸念されます。給料の減額は、モチベーションを低下させ、離職にも繋がりかねません。
そうでなくても人手不足に悩まされている建設業界において、人材の流出は避けなければなりません。そのため、現在、官民一体となって労働環境改善に向けたさまざまな取り組みが行われています。取り組みの詳細については、後ほど詳しく解説します。
建設業の働き方改革が求められる背景
5年間の猶予が与えられたとはいっても、建設業界にとって、長年続いてきた業界の体質を改善し、2024年問題に対応するのは容易ではありません。
それでも、そんな建設業に時間外労働の上限規制が適用され、働き方改革が求められる背景には業界が抱える多くの課題があります。中でも、「人手不足」と「長時間労働」の問題は特に深刻です。
少子高齢化による人手不足
少子高齢化による人手不足は、国内の多くの業界で共通の課題となっていますが、建設業においても例外ではありません。
国土交通省の資料によると、2021年の建設業の就業者数は1997年のピーク時から約29.2%も減少しているという現状があります。
さらに、労働者の高齢化と若手人材の不足も大きな課題となっています。
建設業は、住まいやインフラなど、社会を維持するためになくてはならない仕事です。しかし、その労働環境は「3K」(きつい・汚い・危険)のイメージが強く、若者に敬遠されがちでした。
このまま就業者数の減少が続けば一人あたりの業務負荷が大きくなり、離職率の上昇も懸念されます。このような状況から、労働環境の改善を早急に行う必要があります。
常態化している長時間労働
建設業は、他の業種に比べて労働時間が長い上に休日が少なく、それが常態化しているという課題もあります。
建設業には繁忙期と閑散期が存在しますが、特に公共工事などが集中しやすい9月末・3月末は業務量が急増し、時間外労働時間も増えてしまいがちです。
また、業界内での競争が激化している影響で、案件獲得のため工期の短い案件を無理に受注してしまったり、顧客の急な仕様変更の要望に応えようとして労働時間が長くなってしまったりするケースもあるようです。
企業の信用にも関わる工期の遵守を最優先するあまり、これまで業界全体に時間外労働を当たり前とするような風潮がありました。
このような状況と先述した人手不足の影響もあって、一人あたりの業務量が増えていることも長時間労働に拍車をかけています。
建設業の2024年問題を解決するための具体的な施策
2024年問題の解決に向けて、建設業界では適切な工期の設定や労働時間の管理など、労働環境を良くするためのさまざまな取り組みが行われています。
労働時間を短縮しつつ従来の生産性を確保するためには、業務効率化も欠かせません。限られたリソースを有効活用し、生産性の向上を目指すため、IT技術を用いた業務改善にも期待が高まっています。
では、実際にどのような取り組みが行われているのか、ここでは4つご紹介します。
適切な工期を設定し長時間労働の是正
2024年問題に対応するためには、まず、適切な工期を設定し長時間労働を是正することが求められます。工期の遵守を優先した結果、長時間労働や休日出勤を当たり前としてきた業界の体質を見直さなければなりません。
そのためには、発注者や元請け企業に説明を行って理解を得た上で、無理のない工期を設定する必要があります。
工期の設定は、時間外労働の上限規制や週休2日制・休暇取得の推進を考慮して行うようにします。受注の段階で、不当に短い工期の案件を受けないようにすることも大切です。
また、建設業では現場作業が主体となるため、どうしても天候の影響により進捗が左右されてしまいます。悪天候により作業が進められない場合、時間外労働が増えてしまうことも考えられるので、余裕を持った工期の設定が重要です。
施工条件や生産体制のアセスメントを明確化し、精度の高い工事計画が立てられるような工夫が求められます。
週休2日制の導入を検討する
これまで、建設業では週休1日の企業が多く、週休2日制を導入している企業は2割程度にとどまるなど、休日が少ない傾向にありました。
休日を増やすことで工期が延び、労務費や現場管理費、重機の賃料などのコストが増えることが懸念されていたからです。また、日給制で働く人にとっては、休日が増えることで賃金が下がってしまうという懸念もありました。
そこで、今回の働き方改革では、休日の数に応じた補正係数を算定し、工事費の積算において補正を適用した単価を計上できるように積算基準が改正されました。
他にも週休2日制の導入によって賃金が減ることがないように、休日数に応じて労務費補正を行えるようにするなど、週休2日制の実現に向けた取り組みが行われています。
国土交通省もガイドラインを策定し、週休2日の確保を前提とした工期の設定を求めています。そして、2020年以降の国土交通省からの発注工事については、原則すべて週休2日を実現できる工期設定とされました。
このような取り組みにより、建設業界の週休2日制が推進され、今後業界全体に普及していくことが期待されます。
給与の見直しや社会保険への加入
人手不足を解消するためには、給与の見直しや社会保険への加入など福利厚生の充実も重要です。
建設業界には、社会保険に未加入の企業も多かったのですが、建設業法の改正を受けて2020年10月から社会保険の加入が実質的に義務化されました。加入義務の適用が除外となるケースはあるものの、労働者保護の観点からも社会保険への加入は大切です。
給与面の見直しについては、これまでの経験や技能を正当に評価し、給与が上がっていくという仕組みづくりが求められています。
現在、国土交通省では、建設キャリアアップシステム(CCUS)と呼ばれるクラウドシステムの導入を推奨しています。
これは、技能者の資格や就業履歴などをデータベースに登録・蓄積していくことで、働く場所が変わっても過去の実績や技能を正当に評価し、客観的な評価に基づく処遇に繋げるためのシステムです。
このように、建設業団体と国土交通省が官民一体となって、スキルに応じた給与の引き上げや、若い世代がキャリアパスなどの見通しを持てる仕組みづくりに取り組んでいるのです。
ITツールを導入する
2024年問題への対応において不可欠な労働時間の管理や業務効率化には、ITツールの導入も有効です。
労働時間の管理には、タイムカードやICカードの活用、勤怠管理システムの導入の他、スマホのアプリケーションを使って労働時間の申告をする方法もあります。
業務効率化や生産性向上については、国土交通省も「ICT(情報通信技術)工事」を推奨しており、近年、建設業においても多くの企業がICT化に力を入れています。
そのような変化の中で、タブレット端末とアプリケーションを使った工事進捗情報の共有、ドローンとレーザースキャナーを用いたデジタル測量なども行われるようになりました。
建設業にデジタル技術を活用することには、多くのメリットがあります。
例えば、デジタル技術を用いて計測・計算・検査を行うことで、誤差やチェック漏れを防ぐことができます。また、危険な場所での作業にドローンやICT重機などを活用すれば、安全性の向上も期待できるでしょう。
まとめ
このコラムでは、2024年問題を見据えて建設業界で行われている、さまざまな新しい取り組みをご紹介してきました。
国土交通省も建設業に対する「3K」(きつい・汚い・危険)のイメージを払拭すべく、「給与・休暇・希望」という「新3K」の方針を打ち出し、労働環境の改善に取り組んでいます。
2024年問題と聞くとネガティブに捉えてしまいがちですが、建設業界は、業界の未来に繋がる変革の時を迎えているのではないでしょうか。
建設業の働き方改革の実現に欠かせない、ICT化・業務効率化に必要なアイテムをお探しなら、法人向けオフィス用品通販サイト「スマートオフィス」をぜひご活用ください。
スマートオフィスでは、事務用品やオフィス用品だけでなく、タイムレコーダーや工具類、MRO商品などの現場用品も幅広く取り揃えています。現場用品特集キャンペーンページもご用意しており、購買に関するお悩みも販売店やカスタマーデスクに相談できるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
