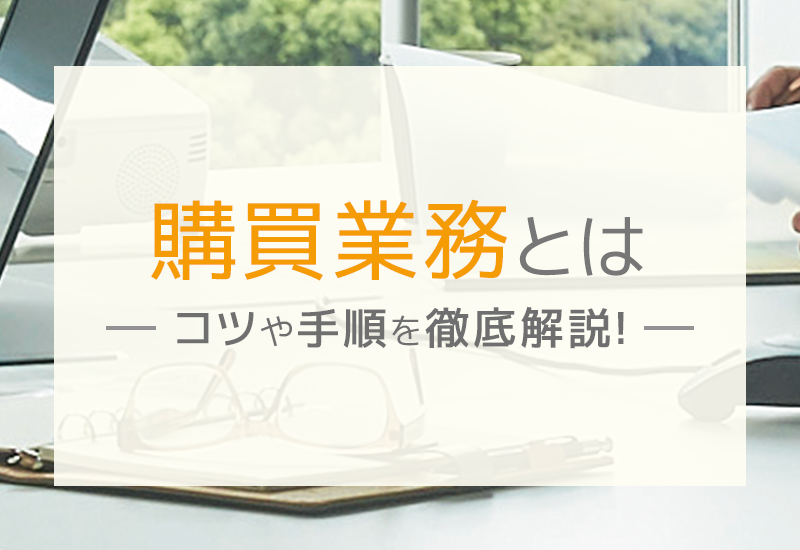
目次
社内業務において、「購買」は企業の利益を左右するとても重要な業務です。購買は、直接材と間接材に大きく分けられます。直接材は企業の商品に必要な原材料などを指します。
一方、間接材は、企業の主要活動に直接必要ないものの、オフィス家具や事務用品など業務活動に必要なものを意味します。直接材に比べ、間接材は少量多品種であるため購買の手間が掛かります。間接材を上手く購買するためには、購買管理の効率化が大切です。
今回は購買業務における課題と解決策についても詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
購買業務を取り巻く環境の変化
近年、日本では物価上昇が著しく、且つ人口減少による働き手不足により、購買業務にかかる工数のコストカットや効率化が重要課題になってきました。
コストの見直しや代替品を考えるなどの必要が出てきたり、購買業務の担当者の属人化を解消し、誰でも操作できるようにシステムを変更したりするなどの変化が生じています。
購買業務とは
購買業務とは企業活動に必要なものを購入することを指します。冒頭で先述したように購買するものは、大きく直接材と間接材に分けられます。それぞれ購入するタイミングによって値段が変わるため、適正な仕入れ先の選定を行ったり、利益率を考慮したりする必要があります。
他にも品質や納品日なども考慮しましょう。仮に品質に問題があるものを購買すると、すぐ壊れてしまい再度買い直す必要があり、企業の利益に損害を与えてしまう可能性があります。
間接材は、企業の主要活動と直接関係がないもののため、予算に対しておさえながら購買しましょう。予算を抑えるために購入するタイミングやサプライヤーをそれぞれ見極め、材料を仕入れることが購買業務においてとても重要です。
調達との違い
調達という言葉をよく耳にしますが、調達は購入するだけではありません。レンタルやリースも含まれるため、購買よりも広い意味になります。物だけでなく人やサービスに対しても調達は使われます。
一方、購買は生産計画に応じて、その時必要なものを選定先から購入することを指すため、調達よりも少し狭い意味になります。
購買業務の流れ
続いて、購買業務の流れについて解説します。業務の流れをしっかり把握することで、課題を見つけ対策を練ることができます。
見積依頼・価格交渉
まずは、見積依頼書を作成し、複数の取引先に見積依頼を行います。見積書依頼は、発注先候補を選定するために行う作業です。
見積書依頼を行うことで、自社が求める内容と一致しているか、支払い方法や保証期間、秘密保護契約が明記されているかなどのチェックができます。
見積依頼書をそれぞれ比較・評価し、条件交渉に移ります。条件交渉は原価や配送料、納期日数などを確認します。
仕入れ先の選定
企業によってサービスが異なることから、複数企業を比較・評価することで自社要求に見合った仕入れ先を見つけられます。
送料自体は高いものの、複数商品を購入すると送料が無料になるサービスなどもあるので、見積書だけでなく付随サービスも考慮しながら選定しましょう。
発注
仕入れ先を決定したら、発注作業を行います。見積書の内容と照らし合わせながら、注文書を作成し、メールやFAXで送信します。最近は、Web上で注文書や請求書の作成、購入履歴の閲覧などが簡単にできるサービスもあります。
Web上で発注業務を完結すると購買情報の管理も楽になります。企業全体で購買情報の共有もできるので、発注の重複ミスを防ぐことができます。
納品処理
仕入れ先から納入後、品数・品質・商品間違いなどがないかチェックします。納期自体に遅れが生じた場合は、依頼先に確認の連絡を取ります。また、注文書とは異なる商品が納入された際にも依頼先に連絡をとり、返品交換の手続きを行います。
その際に、納期日数について確認することが大切です。万が一、納期が遅くなる場合、作業が止まってしまうリスクがあります。納期が遅れる場合、他の取引先からすぐ発注できるよう体制を整えておきましょう。
購買業務における課題
購買業務の流れを一通り解説しましたが、昨今の購買業務はいくつか課題を抱えています。具体的に3つ紹介します。
購買情報を管理できていない
どの取引先から何を何個購入したのかなどの購買情報を、会社全体で把握できていないことが1つ目の課題です。注文書や請求書を一ヶ所に保管せず、部署ごとや購買担当者ごとに保管している場合、購買情報の管理が難しくなります。
また、情報管理の徹底をしていないと、購買担当者による経費の私用利用、横領などの不正が生じてしまう可能性もあります。
購入方法が統一できていない
購買担当が複数いる場合は特に、購入方法を統一していないと発注時に多くの問題が生じます。
複数の担当者が同じ商品を何個も発注していたり、発送手数料や決算手数料などの余計な出費が生じたりなど、発注担当同士で分担やルールを定めていないと経費が無駄に膨らんでしまいます。
購買担当者が複数いる場合は、社内で購買ルールを定めるようにしましょう。
購買業務の煩雑化
最近は、ネットでの購買業務が徐々に増えてきていますが、未だ紙のカタログで注文する企業も数多く存在します。その際、紙カタログで商品を選定したのち、メールや電話で発注するため、購買データの管理が煩雑になってしまいます。
購入する商品が少ない場合や取引先が1社の場合はそこまで煩わしくありませんが、複数の取引先で多くの商品を購入する場合は、注文書や請求書の発行量も多くなります。また、自ら商品を買いに行く場合も、時間と手間がかかります。
購買業務の課題を解決するには
購買業務の課題をそれぞれ解説しました。ここからは、課題の解決方法を紹介します。どこを改善すれば、購買業務の簡素化ができるのかみていきましょう。
現状の把握と見直し
まずは、購買業務に関わる業務を詳細まで洗い出し、無駄がないか検討しましょう。一つひとつ作業に目的とゴールを設定する必要があります。目的とゴールを決めることでどれが必要な作業かを選定できます。
他にも同じ商品を大量発注したり、納期に間に合わない発注をしたりなど人的ミスが起こる原因も洗い出せると良いでしょう。
購買方法の統一化と購買データの一元管理
現状の把握・見直しが完了したら、次は購買方法の統一化をしましょう。購買フローをルール化し、社内統一にすることで購買情報を可視化し、誰でも管理ができるようになります。
また、Webでの発注にすることで、注文書や請求書もデータで作成でき、購買データの管理も可能になります。購入履歴が閲覧できるようになれば、探す手間がなくなるため、追加で同じ商品の購入ができます。
ITシステムの導入・DXの推進
一方でミニマムかつ低コストでスタートする方法もあります。それが、ITシステムの導入やDXの推進です。ITシステムは購買管理システムを簡略化し、購買データを簡単に可視化できます。購買データを可視化することによって、どこでミスが生じたのかが一目で分かり、注文書や請求書を作成する際にも便利になります。
DXについては、社内のペーパーレス化や取引先との契約書作成が簡単にできるサイトを利用するなど購買業務の効率化を図ります。ITシステムの導入やDXの推進をして、購買業務の簡素化を目指しましょう。
まとめ
今回は、購買業務とは何か、購買業務の課題と解決策について解説しました。購買業務は企業にとって重要な役割であり、購買情報の管理が難しいことや作業工程の多さが課題であることがわかりました。
購買業務のルールを明確にし、ITシステムの導入やDXの推進による購買データの一括管理が一番の解決策になります。そこで購買データの一括管理を検討している方に、スマートオフィスの利用をお薦めします。
法人向けオフィス用品通販サイト「スマートオフィス」では、お客様の購買に関するお悩み解決から商品提案・オフィス作りまで、 販売店とスマートオフィスでサポートいたします。
また、予算管理や承認発注などの購買管理ルールをsmartoffice Webで設定し、購入と同時にデータが管理されるので、作業コストが削減できます。この機会にスマートオフィスを利用してみてはいかがでしょうか。
