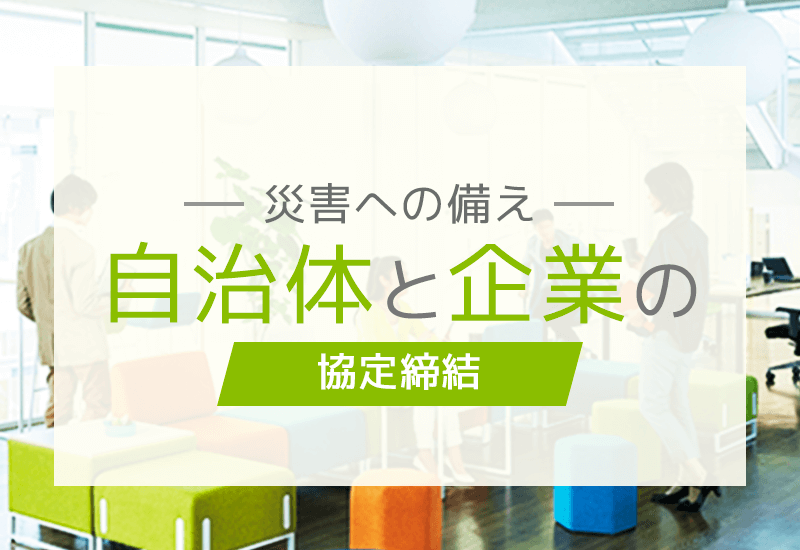
目次
震災、台風、洪水などで被害が出た際に、地域での取り組みや政府から受ける援助以外にも、自治体が企業と共同して復興をサポートするなど、様々な支援の方法があります。これまでに起こった災害経験から企業との連携を強化する自治体が増えています。
今回は、災害に備えて自治体と企業が協定を締結するメリットや実際の事例を紹介しながら、共に助けあう仕組みについて解説します。
企業から地域への支援
商品やサービスで利益を生み、企業として納税することで、地域に貢献する形以外にも企業は様々な方法で地域への支援をしています。ここでは、その支援の形を3つ紹介します。
資金的支援
資金的支援とは主に寄付を行うことを指します。寄付先は社会福祉団体や教育支援団体、自然保護団体など企業によってさまざまです。社会貢献を行うクラウドファンディングへの資金提供もこれに当たります。
上記の間接的な支援の他にも、災害地域に対して直接的に資金援助するといった形がとられる場合もあります。
物的支援
物的支援は企業の持つリソースの一部を地域貢献に使うことを指します。例えば自社の商品を割引で利用できるサービスや、地域住民に企業が所有する施設(ホール・グラウンド・工場など)を利用、見学できるよう開放することなどが挙げられます。
他にも物的支援として挙げられるのは、自社が持つ技術やノウハウの提供や災害地域への救助用品の提供です。近年ではサスティナブルな商品の利用なども、広義の意味で将来を見越した物的支援とされています。
人的支援
人的支援としてよく目にするのは、地域でのゴミ拾い活動や緑化活動ではないでしょうか。その他にも学校などに講師として赴いて地域の子ども達と交流したり、NPO団体と共にボランティア活動を行なったりする場合もあります。
災害時における地域でのボランティア活動や復旧活動における支援も、人的支援の一つと言えるでしょう。このように様々な形で自治体と企業は繋がっています。
災害時における地域と企業の連携
ここからは災害時によく使われる「自助」「共助」「公助」という言葉の概念と、自治体と企業が連携する際の協定内容を紐解きながら、災害時の助け合いについて解説します。
自助・公助・共助について
大規模な災害により社会的リスクが高まったときに、より早く復旧する助けとなる概念に「自助」「共助」「公助」があります。
・「自助」とは、災害発生時に、自分や家族の安全を自ら守ることを指します
・「共助」とは、地域やコミュニティで周囲の人たちと協力し助け合うことを指します
・「公助」とは、国や市町村など公的機関(警察・消防・自衛隊など)からの救助や援助を指します
公助の開始を待つ間に災害直後から始められる助け合いが自助と共助です。自助として日頃から個人や家庭で防災備蓄品を準備しておくこと、共助として会社や地域など所属するコミュニティにおいてもプラスαの準備に加えて、発災時の役割分担を決めておくこと、そしてコミュニティ同士・コミュニティと自治体・自治体同士での連携強化を図ることが災害に強い地域作りに直結します。
共助のメリット
被災した場合に自身と周囲の身の安全が確保(自助)できた後に始まるのが共助です。ここでは、主に防災対策において自治体と企業が協同して行う共助のメリットについて解説します。
災害からの復旧・復興が早まる
共助として災害時に企業の敷地が避難場所として解放される場合があります。安全な避難場所に被災者を誘導すれば人的被害を抑えることが可能です。また、救援情報を自治体と企業が共有し、負傷者の救護が速やかに行われることで地域住民は安心を得ることができます。
企業の持つ商品や防災備蓄品の配布・運搬も協力して行われます。早期に食料など必要な物資を提供しながら、国からの物的支援や人的支援を受け入れる体制(受援体制)も整えておくことで、地域全体の災害からの早期復旧に繋がるのです。
自治体に貢献する企業が認知され地域が盛り上がる
自治体と企業が連携した活動を行うことは、地域住民と企業を繋ぐことにもなります。地域住民への支援を行った企業が認知され、信頼性が高まることにより地域社会は活性化します。
災害からの復旧後、支援を行った企業が地域社会で評価されると、その企業のサービスを使うきっかけや商品を購入する行動に繋がり、地域全体が盛り上がるのです。
自治体と企業が繋がる協定
では、自治体が企業と具体的に繋がるために行う協定にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは2種類の協定について紹介します。
地域防災協定
地域防災協定は、その地域で発生する可能性のある災害を想定した上で、自治体と企業・周辺町会(地域住民)の3者間で協力できる防災対策や災害対応の内容を明記したものです。協定内容は自治体や企業により異なりますが、協定書をもとに平常時の防災活動や災害対応の救援活動が行われます。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
・防災訓練の共同実施
・防災備蓄品を保管する倉庫の提供
災害時応援協定
災害時応援協定とは、災害が起こった際に対応できる人的・物的支援について、自治体と企業間で締結する協定のことです。過去に起きた大災害の経験から、災害時に自治体が企業と連携して応急的な対策を行えるよう、内閣府でも協定の締結を推進しています。
協定内容の一例として以下のようなものが挙げられます。
・避難場所・応急救護所として企業の敷地を提供
・食料の運搬や炊き出しの提供
・救助用の重機やオペレーターの提供
・被災者の移動手段の確保
・医療救護やライフラインの復旧
防災に役に立つ商品を作る企業や取り扱っている企業、企業の社会的責任として防災に取り組む企業の増加に伴い、協定を結び災害時のスムーズな対応を整える自治体は増加傾向にあります。
このような協定が事前に締結されていることにより、災害直後から迅速に救援活動を開始できるのです。
自治体と企業の取り組み事例
ここからは自治体と企業間で具体的に行われている取り組みや締結された協定の一部をご紹介します。
宮城県岩沼市との連携
宮城県岩沼市は2022年10月に「災害時等における物資供給に関する協定」をプラス株式会社ジョインテックスカンパニー(以下、ジョインテックス)と締結しました。岩沼市とジョインテックスではどのような連携がなされているのでしょうか。
災害支援協定を結んだ経緯
岩沼市とジョインテックスが災害支援協定を結ぶきっかけとなったのは東日本大震災で大きな被害を受けた経験です。それまで自治体が行っていた対症療法的対策を見直し、平時からの対策強化と地域住民や企業との協力体制を構築することに重点を置くようになりました。
連携により得られたメリット
想定外の災害発生時に十分な支援を行うためには自治体内の備蓄では限界があるため、企業の持つ幅広い物資やリソースを頼れることは大きなメリットといえます。また全国に展開する企業と連携すれば自治体内の支社や支店が被災してしまった場合でも、被災していない場所からの救援体制をとることができます。
地域で行う防災体験会について
市内の中学校でジョインテックスと協力して防災用品を用いた防災体験会も実施されました。防災体験会の実施は、平時から防災について学ぶきっかけとなり、地域住民の備蓄への意識を高めたり、家族で防災について話したりする機会にも繋がります。
このように、自治体と企業が交流を深めたり連携したりすることは平時から防災意識を高め、災害発生時の市民の行動を変えるきっかけにもなるのです。
愛知県内3市との連携
またジョインテックスでは、2023年9月に愛知県大府市と豊明市、2023年11月に名古屋市とも「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定」を締結しました。
南海トラフ地震、津波、大雨等の大規模災害を想定し、現在の備蓄物資に加えて市からの要請で迅速に物資の供給を行うことになっています。具体的には避難所生活に必要な簡易トイレや非常食などの緊急物資や生活必需品などを保管しており、災害発生時には供給拠点となり支援を行えるよう準備されています。
スマートガバメントとは
最後に、地方公共団体向け調達サービス「スマートガバメント」について紹介します。地方公共団体で必要とされる定番品や、地方公共団体ならではのお悩み解決をサポートする機能を提供しています。
スマートガバメントの災害対策
さらに、スマートガバメントには地方公共団体の持つ防災備蓄品に関する悩みに応える商品や機能が満載です。災害時に役立つ情報を3つの視点から紹介していきます。
防災BCP対策として使えるWeb機能
防災用品の備えには無料で利用できる防災備蓄品管理ツールの「サクッとkeep」が便利です。管理担当者・保管場所・カテゴリー(非常食など)に加え、備蓄数や賞味期限を登録することができ、一度登録してしまえば担当者が変更になった場合もスムーズに引継ぎを行うことができます。
スマートガバメントで購入した商品はお客様の設定により自動的に管理リストに登録され、賞味・消費期限の近づいた備蓄品についてはアラート機能でお知らせすることができます。
防災対策に必要なものが揃うカタログ
スマートガバメントのカタログの特徴として、地方公共団体へのヒアリングを通して選定した幅広いカテゴリーの商品をラインアップしている点が挙げられます。デジタルカタログと紙のカタログ両方を提供しており、必要なシーンに分けてイラスト等で見やすく商品を紹介しています。
他にも、防災備蓄品を購入したいけれど、何をどのくらい準備すればいいのかわからないという自治体へは「サクッとstock」の利用もお薦めです。「サクッとstock」では、備えたい人数・日数・カテゴリー(保存食・携帯トイレなど)を選択するだけで、簡単に必要な量の見積もりを確認し購入することができます。
お困りごとへの相談が可能
調達をはじめとしたさまざまな業務の効率化や、災害に備えた防災備蓄品の購入管理について、地元の登録販売店やスマートガバメントの担当営業へ直接ご相談していただくことも可能です。地方公共団体のお悩みに寄り添い、地元の登録販売店とタッグを組んでサポートいたします。
防災備蓄用品管理代行サービス
防災備蓄品の管理や購入にリソースを割けない場合などには、「防災備蓄用品管理代行サービス」もあります。当サービスは期限の異なる多くの商品管理や保管物の照合・棚卸作業にかかる面倒な作業を一括で引き受けるサービスです。
一度備えても、水や食料品の賞味期限確認、消耗品の消費期限、備品の電池切れや稼働確認など手間のかかる作業が不定期に訪れるのが防災管理業務です。大きな負担となりがちな防災備蓄品の管理をアウトソースすることで、必要なコア業務へ人的資源の投入も可能となります。
まとめ
今回は、災害に負けない自治体作りの一つとして企業などと共助する重要性について解説してきました。地震や台風など自然災害のリスクを多くもつ日本において、平時から自治体と企業がしっかりとした繋がりを持ち、災害への対策強化に取り組んでおくことはとても大切です。
自治体での災害準備には、スマートガバメントをはじめとした防災にも役立つツールをご活用ください。防災備蓄品の購入から管理まで、ご相談に応じて個別にサポートいたします。
