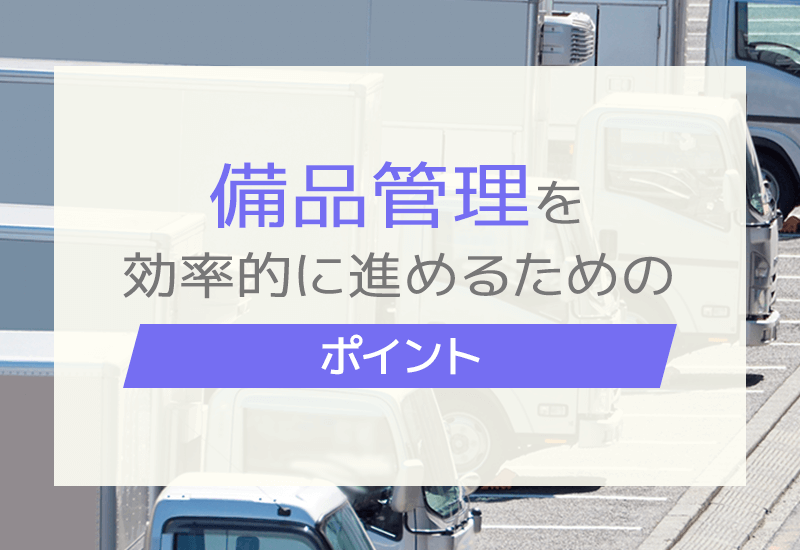
目次
自社でも備品管理の導入を検討しているものの、どのようなメリットがあるのか、どのように進めるのが良いのかと頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、備品管理のメリットをはじめ、備品管理を効率的に進めるためのポイントや具体的な手順、始める最適な時期について解説します。ぜひ導入を検討されている方は、ご参考ください。
備品管理とは
備品管理とは、会社で使用されるパソコンやプリンタなどのデジタルデバイスをはじめ、デスクやチェア、キャビネットといった大型の備品も含めた個数や状態を管理することです。
会社の備品管理台帳に登録される資産対象です。物品管理とも呼ばれ、各個数を管理することが第一の目的とされています。
自社の備品を正しく把握できていないと探すのに手間がかかったり、無駄に発注してしまったりといった問題が起きます。また、会社で使用されるものは種類や数も多く管理も大変なため、定期的に備品管理を行うことがお薦めです。
備品と消耗品の違い
備品と消耗品の違いは、取得価額と使用可能期間にあります。他にも、備品は業務上で必要であるため常に備えておくもの、消耗品は一次的に使用して破棄されるようなものが該当します。
一般的に、備品は取得価額が10万円〜30万円未満で、使用可能期間が1年以上のものを指します。一方、消耗品は取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満である場合が該当します。
<それぞれの具体例>
■備品:椅子、机、キャビネット、プリンタ、パソコンなど
■消耗品:ボールペン、付箋、ノート、トイレットペーパー、プリンタ用紙など
備品管理のメリット
備品管理は、社内で使用される備品の数や状態を把握することです。例えば、リモートワークを導入する企業であれば、従業員数が多いほどパソコン等のデジタルデバイスの数を正確に把握するのは手間がかかる作業です。それでも備品管理を行うメリットとは何でしょうか。
経費削減
正しく備品の数や状態を把握することは、経費削減に繋がります。在庫数や管理が行き届いていないと、ほとんど使用しない備品を新たに発注してしまったり、無駄な在庫を抱えることになるでしょう。そのため、適切な量の在庫を保管したり、無駄な発注を防いだりすることは、結果として経費削減となります。
業務効率化
備品の所在を把握することで素早く備品を探すことができるようになり、業務の効率化を実現します。
例えば、どこにあるのかがわからず探したり、在庫があるにも関わらず業務中に慌てて新規で発注したり、在庫がないため業務が止まってしまうといった無駄を省くことができます。的確に備品の状況を把握することは、結果として業務の効率化へと繋がるのです。
セキュリティ向上
パソコンなどの備品の数や場所を正しく把握することは、セキュリティ向上へと繋がります。
備品を簡単に持ち出せる場所に保管していれば、いつでも持ち出せるリスクが生まれます。また、パソコンなどの備品を誰が保有しているか正しく把握できていない場合、誰かに持ち出されて情報漏洩へと繋がる可能性もあるでしょう。
最悪の場合、個人情報や機密情報の漏洩によって、企業としての信頼を失うこともあり得るため、セキュリティ環境を向上させることは多くのメリットがあります。
従業員満足度の向上
必要なタイミングで備品を手に入れることができる状態は、従業員満足度の向上にも寄与します。
しっかり備品の数や所在が管理できている会社では、従業員が必要な時に必要な備品を提供できます。そのため、備品がない、見つからないといったストレスなく働くことができます。
また、備品がしっかりと整っている会社は清潔であるため、オフィス環境の向上や働く従業員の創造性を高めるといった効果も期待できます。
効率的な備品管理のポイント
備品管理によるメリットについてご紹介しましたが、「具体的な進め方が分からない」という方もいるかと思います。ここでは、効率的に備品管理を進めるためのポイントを、一つひとつ順を追ってご紹介します。
備品の所有者・現状数を把握する
備品管理を行うにあたって重要なのは、現状の数を正しく把握することです。まずは一つひとつの備品の状況や状態を確認しておきましょう。
欠品の把握はもちろん、破損して状態が悪い場合は適切なタイミングで使用できません。
また、備品の所有者を確認することも備品管理の一つです。例えば、製造部門の備品を総務部が把握すると無駄が出ることもあるため、担当部署や所有者が確認・把握すると良いでしょう。
備品を分類する
一言で部品と言っても、分類によって管理方法が異なります。例えば、パソコンやプリンタなどのOA機器と、備え付けの机やキャビネットといった什器は取り扱いが異なるので、分類しましょう。
但し、取得形態は会社によって異なります。会社によっては、机や椅子は購入しているが、キャビネットはレンタルといった場合もあるでしょう。
自社で購入した物かどうかを確認した上で、「よく使う物」「あまり使わない物」といった具合で、使用頻度ごとに分類すると良いでしょう。
備品管理フローを作成する
備品の整理ができたら、次は備品管理のフローを作ります。前述した通り、パソコンやプリンタなどの高価なOA機器を購入するのであれば、上司の承認や稟議が必要となるでしょう。一方、比較的使用頻度の高い文房具などは、稟議なしで購入できることが多いため運用フローが異なります。
このような備品による管理フローを整理・確認しておくことは、後の管理がしやすくなるためお薦めです。
備品管理台帳を作成する
続いて、備品を管理するための台帳を作成します。下記のような内容を記載した台帳を作成しておくことで、備品の所在を見える化できます。
・管理番号
・物品名
・物品カテゴリ
・購入場所
・購入日
・数量
・登録日
・登録者
・更新日
・更新者
・保管場所
・利用状況
備品のラベリングと整理整頓する
管理台帳に記載した番号を、備品にもラベリングします。こうすることで、台帳を見ただけで備品の所在がわかるため便利です。
また、分類したカテゴリ別に色を分けておくと、何がどこにあるのかが分かりやすくなります。さらに色分けした台帳を管理する場所も統一すれば、一層管理しやすくなるでしょう。
備品管理のルールを周知する
管理台帳や備品の管理方法が決定したら、従業員にも備品管理のルールについて周知をしましょう。備品管理台帳の分類についてや書き方、備品の置き場所など、自社で決定したルールについて従業員に伝えます。
周知が漏れると、せっかく整理した備品の置き場所が分からなくなったり、管理台帳の内容に不備があったりと運用が上手く回らないため、注意しましょう。結果として、管理台帳を作成した人しか分からないといった属人化を防ぐことにも繋がります。
定期的な見直しやアップデートする
このように備品管理のルールや運用を見直すことができたら、最後は定期的に備品管理を実施しましょう。
定期的に備品の状態等を見直すことによって、無駄な備品を抱えることがありません。あまり使われていない備品は、発注数を見直すことによって無駄なコストを抑えることにも繋がるでしょう。
管理台帳の内容を最新の状態にすることで、台帳を見ればすぐ備品について把握できます。
備品管理を見直すべきタイミング
これまで「備品管理に取り組んだことがない」、自社に「備品管理の体制がない」といった企業であれば、いつ備品管理に着手すべきと思われるかもしれません。
最初の体制整備の負荷をはじめ、時間が経過すればするほど企業規模は自然と大きくなり、管理すべき備品も増加します。
そのため、備品管理はなるべく早く着手するのがベストです。それでは、いつ始めるべきなのかタイミングをご紹介します。
新しく備品を購入するとき
新しく備品を購入する際は、備品管理を見直す絶好のタイミングです。新たな分類の備品および、既存の備品を追加するタイミングの可能性があります。いずれにせよ、自社の備品状態を購入時に見直し、最新の状態が把握できるようにしましょう。
規模が大きい会社になると、備品の数も膨大なはずです。新しく増えるタイミングで是非見直してみましょう。
備品が紛失、破損したとき
備品が無くなった時や紛失した時は、オフィスの様々な場所を探す手間や、今ある備品を一つひとつ見直したり探したりするでしょう。そのため、備品紛失のタイミングは、備品管理を始める良いチャンスです。
代替品はないのか、在庫は何個あるのか、といった項目と併せて、既存の備品を台帳に付けて管理できるようにしましょう。
不要な備品が増加したとき
自社に「いらない備品が増えた」と感じる時も、備品管理を始めるタイミングです。
本来、必要のない備品の発注を継続してしまっている可能性も考えられるでしょう。無駄な在庫を抱えてスペースを奪っている可能性も考えられます。費用面やスペース面においても不要なコストは、会社として早めに見直すべきでしょう。
棚卸しをするとき
棚卸しとは、自社内に滞留する在庫の数を確認し、棚卸資産の金額を確認するためのものです。備品を含めた自社の状態を把握する上で、絶好のタイミングでしょう。なお、棚卸資産とは企業が消費する目的で購入したけれども、残ってしまっている資産を指します。
このような棚卸資産を把握し、経費処理することは会計上重要な工程です。企業として、正しく取り組みましょう。
備品管理台帳作成のポイント
社内にある全ての備品の状態や所在を確認し記載する管理台帳ですが、実際に導入するとなると「どのような項目を記載すれば良いの?」と悩む方も多いでしょう。一つひとつ解説します。
管理番号
管理番号は識別番号とも呼ばれ、備品の一つひとつに付けられる番号を指します。
印刷して、各備品に貼り付けると管理しやすいでしょう。特に、購入したパソコンなどは連番にすることで、購入時期が把握しやすいといったメリットもあります。
管理台帳は、一番左端に管理番号の列を作成しておくと視認性も高く、管理が容易です。
備品の名前
パソコンやプリンタといったOA機器は、メーカーや型番等があるため、管理する際は物品名と併せて記載するのがお薦めです。
例えば「メーカー:〇〇 型番:〇〇」といった具合で、物品名と併記しましょう。
カテゴリ
物品数が増加すると管理が難しくなるため、事前に備品をカテゴリ分けしておきましょう。例えば、パソコンやプリンタ等は「OA機器」、オフィスの机や椅子は「オフィス家具」などと、ジャンル別に振り分けておくと、後の管理が容易です。
購入日・購入数量・現在の数量
購入日や購入数量、現状の数量を把握することも重要です。特に、文房具などの消耗品は購入日を記載しておくことで、購入から破棄にいたるまでの日数や発注頻度を把握し、次に無くなりそうなタイミングで発注を行うことができます。
また、将来的に必要な予算の見立てができるようになるため、計上予算の見立てが精緻にできるでしょう。
備品管理を効率化するためにIT化もおすすめ
備品管理の効率化にはデータベースをIT化することがお薦めです。
検索や情報共有のスピード感はもちろん、情報を一つの場所にまとめる一元管理といった観点でも便利です。そのため、ExcelやGoogleスプレッドシートといったITツールを駆使しましょう。
但し、ExcelやGoogleスプレッドシートは、あまりに情報が多くなると動作が重くなり、取り扱いづらくなる可能性も高いため、データ量が膨大な場合は備品管理システムを検討すると良いでしょう。いずれにしても、情報をすぐ取り出せるようにITツールを駆使することが重要です。
まとめ
備品管理は、備品の状態や数を把握するだけでなく、会社のお金を正しく把握する一つの方法です。無駄なリスクやコストを省くためにも、早いうちにITツールを駆使して、備品管理を導入しておきましょう。
なお、予算に応じた備品の購入や自社に最適なものを検討されている場合は、数々の商品を取り扱っている法人向けオフィス用品通販サイトの「スマートオフィス」がお薦めです。販売店とカスタマーデスクに相談しながら購買管理が行えるため、ぜひご検討ください。
