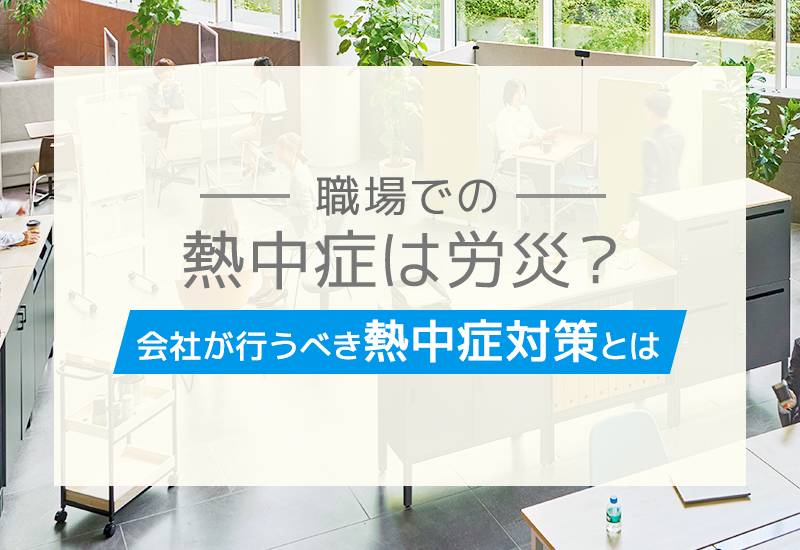
目次
地球温暖化が進む中、熱中症で救急搬送される人は後を絶ちません。そして、職場においても、熱中症による死傷者が毎年数多く報告されているという現状があります。
職場で熱中症が発生してしまった場合の対応や労災(労働災害)認定について、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、職場での熱中症が労災になるのかという疑問にお答えするとともに、従業員の命を守るために会社が担う責任、行うべき熱中症対策や応急処置についても解説します。ぜひ、参考にしてください。
熱中症とは
熱中症とは、高温多湿な環境下において体温調整機能がうまく働かなくなったり、体内の水分・塩分のバランスが崩れてしまったりして起こる症状の総称です。
重症度は3段階に分かれており、軽症ではめまいや大量の発汗、中等症では頭痛や吐き気などの症状が出ます。さらに重症化すると意識障害やけいれんが起こり、救急搬送が必要になります。
熱中症は最悪の場合、死に至るので速やかに対処しなければなりません。
熱中症はさまざまな場所で発生していますが、職場での熱中症による健康被害も毎年多く報告されています。ここでは、熱中症が発生しやすい業種と場所について詳しく見ていきましょう。
熱中症が発生しやすい業種
熱中症が発生しやすい業種は、建設業・製造業・運送業・警備業などです。特に建設業と製造業は熱中症による死傷者数が多く、この2業種だけで全体の4割程度を占めます。
このような業種で熱中症が多く発生している背景には、高温多湿の場所での作業の多さや、身体を動かす時間が長く、持ち場を離れることが難しいといった現場の状況があります。
熱中症が発生しやすい場所
熱中症が発生しやすい場所には、日差しの強い屋外や高温多湿の場所が挙げられます。しかし、屋内でも油断はできません。
実際に製造業における熱中症は、工場内などの屋内で発生するケースも多くなっています。
特に風通しの悪い場所や高温になる場所、発熱体の近くなどで作業する際には注意が必要です。
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、労働契約法第5条において使用者に課せられた「従業員が命や身体の安全を確保しながら働けるように必要な配慮をする」という義務のことです。
労働契約法には罰則はありませんが、この義務を怠った場合には損害賠償責任を問われることがあります。
従業員の熱中症が安全配慮義務違反になるケース
安全配慮義務の対象には業務に関わる熱中症も含まれ、厚生労働省は「職場における熱中症の予防について」という通達を出しています。
この通達の中に、WBGT値(暑さ指数)の活用や熱中症予防対策として必要な措置(作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育・救急処置)に関する記載があります。これらの措置を怠ると、安全配慮義務違反とみなされる可能性があるので注意しなければなりません。
職場での熱中症は労災になる?
労災(労働災害)とは勤務中の事故、業務を原因とする病気・怪我・障害・死亡などのことです。職場での熱中症が労災認定された場合は、労災保険から療養給付や休業給付など、さまざまな補償を受けられます。
ただし、職場での熱中症には、労災認定されるケースと労災認定されないケースがあります。どのようなケースが該当するのか見ていきましょう。
労災認定されるケース
職場での熱中症が労災認定されるためには、一般的認定要件と医学的診断要件という2つの要件に該当する必要があります。
一般的認定要件
一般的認定要件とは、熱中症の発症が業務に起因したものであるかを判断するための条件で、内容は以下の通りです。
・業務上の突発的またはその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること
・当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後から発病までの時間的間隔などにより、災害と疾病の間に因果関係が認められること
・業務に起因しない他の原因で発病(または増悪)したものではないこと
この要件の認定に関しては、さらに作業環境・労働時間・作業内容・作業場の温湿度条件・本人の身体状況や服装などの総合的判断により決定されます。
医学的診断要件
医学的診断要件とは、従業員が発症した疾病が熱中症であるかを判断するための条件で、以下の内容をもとに判断されます。
・作業条件および温湿度条件などの把握
・一般症状の視診(けいれん、意識障害など)および体温の測定
・作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかんなどによる意識障害などとの鑑別診断
労災認定されないケース
職場での熱中症が労災認定されないのは、業務とは別の要因によって熱中症を発症したと考えられるケースです。
具体的には、寝不足や前日の飲酒、持病によって発生したもの、自宅が暑かったといったケースなどがこれに当てはまります。
会社が行うべき熱中症対策
熱中症リスク低減のために、会社はどのような対策をすれば良いのでしょうか。ここでは、会社が行うべき熱中症対策をさまざまな観点からご紹介します。
作業環境管理
まず行うべきなのは作業環境管理です。従業員の作業場所や作業環境を会社側がしっかりと管理しなければなりません。
そのためには、WBGT値(暑さ指数)の活用と休憩場所の整備が大切になります。
WBGT値(暑さ指数)の活用
熱中症対策には暑熱状況の把握が欠かせません。暑熱状況を把握するために、WGBT値(暑さ指数)という指標を活用しましょう。
WGBT値はWGBT指数計を使って測定します。同じ作業現場であっても、暑さは場所ごとに異なります。測定は1か所で行うのではなく、実際に作業する場所ごとに行うようにしてください。
測定したWGBT値が基準値を超えている、または超える恐れがある場合には、作業場所の変更を検討しましょう。場所の変更が難しい場合は、冷房の使用や通風の確保などによってWGBT値を下げる工夫が必要です。
WGBT値が高い時は、作業の中止や休憩時間の確保、単独作業を控えるなどの対策も有効です。
休憩場所の整備
熱中症になりやすい環境で作業する時は、休憩場所の整備が欠かせません。冷房設備のある場所や日陰など、涼しい休憩場所を設けるようにしてください。
身体を冷やすことができるようにシャワーや水風呂などを設置したり、作業場所やその近くに冷たいおしぼりや瞬間冷却パックを備えておいたりするのも効果的です。また、水分と塩分を定期的に補給できるように飲料水や塩飴なども備えておきましょう。
他にも、身体状況を確認できるように体温計などを備えておくことが推奨されています。
従業員の作業管理
環境整備だけでなく、従業員の作業管理を行うことも大切です。どのような対策ができるのか、具体的にご紹介します。
作業時間の短縮
高温多湿の場所ではWGBT値に応じて作業を中止したり、こまめに休憩時間を確保したりするなど、作業時間を短縮するための工夫が求められます。
特に暑くなり始めの季節は、身体が暑さに慣れていないため熱中症を発症しやすい時期です。この時期は、管理監督者に対して連続作業時間を短くするように指導しましょう。
服装
熱中症になりにくい服装を心がけ、熱を吸収したり保熱したりしやすい服は避けるのが無難です。透湿性・通気性の良い服がお薦めです。
また、直射日光の下で作業をする従業員には、通気性の良い帽子を着用させるようにしましょう。このような服装に関する熱中症対策は、従業員まかせにするのではなく会社側が行うようにしてください。
水分・塩分の摂取
熱中症の予防には水分と塩分の摂取が有効です。会社で飲料水やスポーツドリンク、塩飴などを準備したり、自動販売機を設置したりするようにしましょう。
脱水症状は、自覚症状があまりなくても進行していることがあります。自覚症状の有無に関わらず、作業前後や作業中には水分・塩分を摂取するように指導してください。
作業中の定期的な摂取を確認するためには、巡視における確認や摂取管理のための表の作成を行うことが効果的です。
従業員の健康管理
従業員の健康管理も、熱中症予防において非常に重要です。作業開始前に従業員の健康状態を把握し、作業中も定期的に確認を行うようにします。
特に高温多湿の作業場所では、巡視や声かけを頻繁に行うことで従業員の異変に速やかに対処できます。複数の作業者がいる場合は、お互いの健康状態に留意させることも大切です。
また、体調不良や睡眠不足、前日の飲酒、朝食の未摂取などが熱中症の発症に影響を与えることがあります。そのような日頃の健康管理について、従業員に指導を行いましょう。
持病などで熱中症リスクが高い従業員に対しては、作業の可否や留意事項について主治医・産業医の意見を聞き、就業場所や作業内容の変更を検討してください。
熱中症対策・対応マニュアルの策定
熱中症対策・対応マニュアルも策定しましょう。衛生管理者などを中心とした管理体制を整えた上で、熱中症予防のための対策・熱中症発生時の対応についてマニュアルにまとめておきます。
このマニュアルを従業員に周知しておくことが、緊急時の速やかな対応に繋がります。
熱中症予防の教育・研修
マニュアルの周知だけでなく、従業員に熱中症予防の教育・研修を行うことも熱中症対策として有効です。
高温多湿の場所で作業に従事させる場合には、管理者による適切な作業管理と従業員自身による健康管理がとても大切です。管理者・従業員の双方に対して、熱中症の事例や症状、予防法、緊急時の救急処置などに関する労働衛生教育を行うようにしましょう。
もし会社で熱中症が発生してしまった場合
どんなに対策を行っていても、熱中症が発生してしまう可能性はあります。もし会社で熱中症が発生してしまった場合には、適切な応急処置が命を守ることに直結します。
熱中症は急速に重症化することもあるため、速やかに応急処置を行わなければなりません。意識がはっきりしない場合や意識がない場合、重症の場合はすぐに救急車を呼び、まず涼しい場所に移動させて身体を冷やしてください。これは軽症や中等症で、救急車の要請を行っていない場合も同様です。
次に衣類をゆるめ、自分で飲める場合にはスポーツ飲料や経口補水液を飲ませて、水分・塩分の補給を行います。
身体を冷やす際には、皮膚を濡らして扇風機やうちわで風を送ったり、氷やアイスパックで冷やしたりするのも効果的です。軽症であれば、これらの処置だけでも症状がおさまります。
上記のような処置をしても症状が改善しない場合、意識はあっても症状が強い場合、嘔吐などで水分補給ができない場合には、医療機関に連れて行くようにしてください。
まとめ
このコラムでは、熱中症が発生しやすい状況やその対処法、安全配慮義務など職場における熱中症について詳しく解説しました。
熱中症は対応が遅れてしまうと命を落とす危険もありますが、正しい知識を身に付けていれば発生を予防できます。
熱中症になりやすい環境で従業員の命を守るためには、休憩場所の整備が欠かせません。
休憩場所などに備える熱中症対策グッズをお探しなら、品揃えの豊富な法人向けオフィス用品通販サイト「スマートオフィス」がお薦めです。商品に関する相談など購買サポートも行っているので、ぜひご活用ください。
