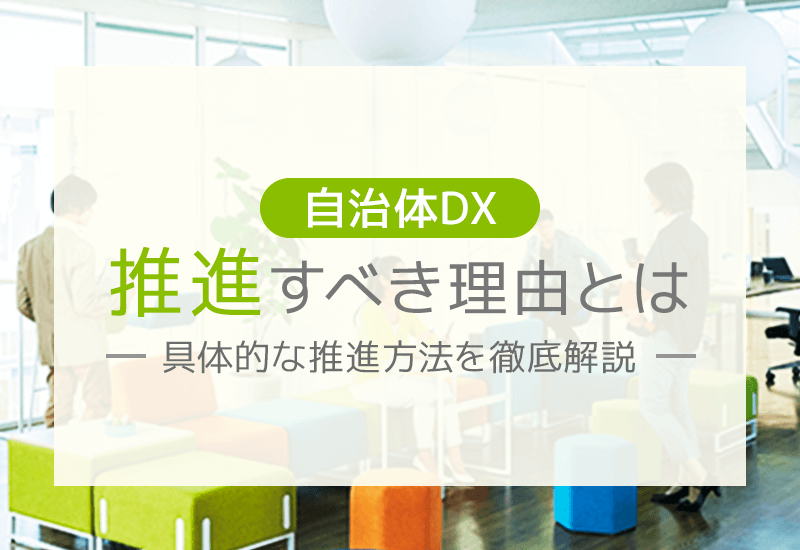
目次
2020年12月25日、政府は「デジタル・ガバメント計画」を閣議決定し、その中の1つとして自治体DXを推進することを決めました。自治体DXは、自治体の業務においてITを利用し作業員の負担を少しでも減らしていくことを目的としていますが、そもそも自治体DXとはどのような取り組みなのでしょうか。
自治体DXとは
自治体DXとは、自治体がIT技術を利用し業務効率を上げ、行政サービスの向上を目指す取り組みのことを指します。DXとはデジタル・トランスフォーメーションの略で、紙を使用した業務が多い自治体において、今後さらに積極的に取り組むべきといえるでしょう。
自治体の業務効率が向上できれば、行政サービスを迅速に行うことができ、住民の要望に対してもすぐに応えることができるようになります。
自治体がDXを推進する背景
自治体も時代のニーズに合わせて動かなければなりません。ここからは、自治体がDXを推進すべき背景について3つ解説します。
少子高齢化
まずは、少子高齢化による働き手の減少です。さらに人口減少により自治体同士で合併する地域もあり、地域の規模が大きくなっても人手不足は加速しています。
その一方で、住民のニーズが多様化し業務内容は年々増えているのが現状です。そこで、DXに取り組むことにより、デジタルで業務管理ができ作業時間の短縮に繋がります。働き手不足の自治体でも業務をカバーできるようにするために、自治体DXの導入が必要不可欠です。
住民のニーズが多様化
次に、住民のニーズが多様化していることもDXを推進する背景となっています。戸籍や税金、マイナンバーカードなど、自治体で行う手続きの数が増えているためです。
自治体は、分野ごとに分かれてチームを組み作業をしていますが、それでも住民のニーズに全て応えるのには相当な時間を要します。そこで、DXに取り組むことにより住民の要望に素早く応えられるようになります。
デジタル技術の普及
最後にデジタル技術の普及です。 自治体の業務にはアナログ作業が多くありますが、近年はハンコ業務やFAXを原則廃止とする方針が発表されるなど、自治体のおかれている環境も少しずつ変化しています。また、住民においてもパソコン・スマートフォンの普及率が上がり、手軽に行政サービスを受けられる時代になりました。
例えば、住民は行政サービスの手続きをする際、従来は来庁して指定用紙へ記入し、窓口で提出をする必要がありました。ところが、デジタル技術が普及したことによってWeb上で完結できることが増え、来庁せずとも手続きが完了するケースが増えました。また、自治体側も来庁予約により事前に準備ができるようになり、行政サービス手続きの効率化が図れるようになりました。
自治体DXを推進するメリット
ここからは、自治体DXを推進するメリットについて解説します。自治体DXに取り組むと、自治体も住民も行政サービスの手続きが楽になります。今回は3つご紹介しますので、参考にしてみてください。
役所内の業務効率化
まずは、役所内の業務効率化です。DXを推進することで、オンライン上で多くの手続きができるようになり、窓口業務の減少が見込めます。また、紙のやりとりが少なくなることで、少子高齢化の時代でも少ない人数で業務の効率化を実現できます。
個人情報漏洩の防止
次に個人情報漏洩の防止です。DXに取り組むことで書類の手続きが減るので、書類紛失による情報漏洩や誤配送を防止できます。
しかし、オンライン上でも情報が漏洩する可能性はゼロではありません。端末やWebサイトのセキュリティ対策や、個人情報の管理業務を定期的に行うようにしましょう。
地域社会の活性化
最後に、地域社会の活性化です。例えば、テレワーク拠点・コワーキングスペースの整備、公共フリーWi-Fiなどの整備によって場所を選ばずに仕事ができるので、地方への移住促進にも繋がります。
その他にも、SNSを活用して情報発信を行うことで、気軽に住民と情報共有ができたり、住民に寄り添ったサービスを提供できたりするメリットがあります。さらにSNSを通じてイベントや行事を住民と企画・開催することで、自治体と住民の交流も深めることもできるでしょう。
自治体DXを推進するために
DXを推進するためには何から始めれば良いのでしょうか。まずはDXの取り組みを理解して、焦らず対応できるようにしましょう。詳しく解説しますので、参考にしてみてください。
自治体DX推進計画を参考にする
まず、総務省が策定している「自治体DX推進計画」を参考にしましょう。計画の対象期間は2021年1月から2026年3月までです。
期間内に、ガバメントクラウドの検討や政府の動向を確認しながら作業を行います。ガバメントクラウドを活用することで、住民がいつでもどこでも行政サービスを受けられるようになります。
推進をステップに分けて進めていく
自治体DX推進計画の内容を把握できたら、次は推進をステップごとに進めていきましょう。4つのステップを的確に行うことで、DXを適切に推進することができます。1つずつ確認していきましょう。
ステップ1:DXに対する知識を深める
まずは、DXがどのような取り組みなのかを理解しましょう。初期段階で推進する担当者や責任者の知識を深めることが大切です。
担当者や責任者から会議等で職員全体にDXの取り組みについて伝えることで、認識共有でき実際に推進する際もスムーズに行えます。知識を深めることで実際にDXを推進すべきかどうかの検討も可能となります。
ここからは実際にDXの取り組みをしている地域をみていきましょう。株式会社日本総合研究所の研究(※1)では、2022年5月時点で自治体DXの推進が一番進んでいるのは、神奈川県です。次いで東京都、愛知県、福井県、静岡県となりました。区や市が多い地域では、DXが先進的に取り組まれていることがわかります。
神戸大学経済経営研究所教授である浜口伸明氏(※2)の研究では、2022年10月時点で全国747の自治体のうち、文書のデジタル化を部分的に導入しているのは261ヵ所、本格実施しているのが101ヵ所でした。
また、オンライン上で手続きができるシステムを部分的に導入しているのが270ヵ所、本格実施している自治体は88ヵ所で、まだまだ実施している地域が少ないことがわかります。
※1出典:株式会社日本総合研究所の研究(参照 2023-01-29)
※2出典:浜口 伸明「自治体DXの実証研究」経済産業研究所(参照 2023-01-29)
人口の少ない地域では、自治体DXに取り組んでいる地域は多くありません。しかし、人口が減少している地域も自治体DXを導入してオンライン上で行政の手続きができれば、自治体の負担を減らすことができ、人口増加への取り組みにさらに焦点を当てることができるでしょう。
ステップ2:全体方針を決める
DXに対する理解を深めたら次に全体方針を決めましょう。どのようにDXを推進するのかを検討できます。自治体の課題を明確にし、DXを推進することでどんなメリットがあるのかを考えましょう。
さらに、期日や役割をはっきり決めることで作業内容が明確になり、DXの取り組みをスムーズに行うことが可能になります。
ステップ3:推進体制の整備
全体方針が決まったら、推進体制を整えましょう。DX専門部門を設置し、担当者や責任者を筆頭にチームを構成します。デジタル人材の育成も欠かせないため、教育できるシステムを作る必要があります。
DXを専門とする部門は、他の部門よりもITに詳しい人材を選びましょう。電子機器の急な故障やデータ不良にも対応できる人材が良いでしょう。
ステップ4:DX施策の実施
最後に全体方針やDX専門部門で決定したことを実践してみましょう。2026年3月までは自治体DX推進期間です。この期間は目標達成時期になるので、必ず2026年3月までに取り組む必要はありません。
2026年以降も自治体DXを推進している可能性もあるので、最新の情報を都度チェックしましょう。また、政府の動向により急な変更事項もあるかもしれません。その場合、臨機応変に対応できるよう準備しておくことをお薦めします。
取り組みやすい自治体DXの実例
最後に取り組みやすい自治体DXの実例を紹介します。自治体DXを大変な作業だと感じている方も多いでしょう。しかし中には取り組みやすいDXもあります。少しでも作業負担を減らしたいと考えている方は、これから紹介する実例を参考にしてみてください。
ペーパーレス
1つ目は、ペーパーレスの実施です。ハンコを不要にすることや申請書類のデジタル化はよく耳にするでしょう。それだけでも業務を簡素化できます。
ペーパーレスにより、経費削減が可能になります。書類を処理する時間も減り、他の業務に時間を割くことができます。ペーパーレスが環境保全にもつながるので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
物品調達のシステム化
2つ目は物品調達のシステム化です。物品調達のシステム化を実現する方法の一つとしてWeb利用を行うと、1つのサイトで必要なものを同時に発注できるので注文の回数を削減でき、伝票や請求書の発行も簡単になります。
人手不足に悩む自治体にお薦めするサービスの1つとして、プラス株式会社ジョインテックスカンパニーが運営する地方公共団体に特化した調達サービス「スマートガバメント」があります。
こちらのサービスについては後ほど詳しく紹介するので、参考にしてみてください。
RPAの導入
3つ目はPRAの導入です。RPAとはパソコンで行う定型作業を自動化するツールを指します。パソコンの定型作業は時間がかかる上に、入力ミスも増え作業員の負担になります。RPAを導入することで他の作業に時間を使うことができ、業務効率化を実現できます。
AIチャットボットやFAQシステムの導入
最後にAIチャットポットやFAQシステムの導入です。エントランスや窓口付近、もしくは自治体のホームページなどにAIチャットボットやFAQシステムを導入することで人手不足が解消できます。
まとめ
今回は自治体DXの推進について解説しました。DXを推進している自治体ほど、行政業務の簡素化、業務効率の向上が実現できていることが分かりました。これからDXの取り組みを考えている方は、ぜひこのコラムを参考に前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
また、地方公共団体向けの調達サービス「スマートガバメント」では、物品調達をはじめとする様々な業務の効率化をお手伝いしています。複数の地元販売店へWebで一斉見積もりができる機能や、必要なときに見積書・納品書・請求書を出力・保存できる機能などを活用して、自治体DXを始めてみませんか。
