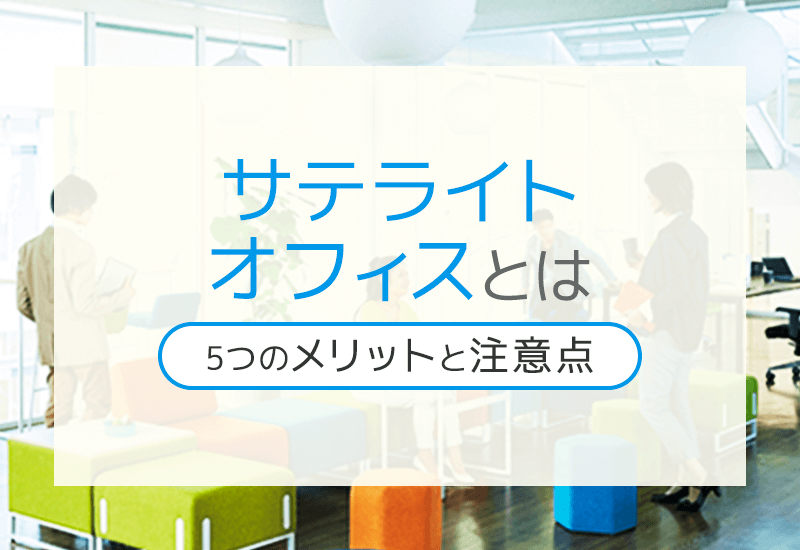
目次
コロナ禍を経て、決められた場所での勤務形態から、多様な場所での働き方へ変化する今、サテライトオフィスが注目されています。サテライトオフィスに興味はあるけれど、設置に対する情報不足や社員の評価方法などの課題から、運用に踏み出せないとお悩みではありませんか。
そこで今回のコラムではサテライトオフィスの種類や設置するメリット、設置に際しての注意点まで分かりやすく解説していきます。
今、注目されているサテライトオフィスとは
サテライトオフィスは「衛星(satellite)」になぞらえて、企業の本拠地から離れた場所に設置された小規模なワーキングスペースに対して名付けられました。1980年代に初めて日本で導入されたサテライトオフィスですが、2020年から施行された「働き方改革」への対策やコロナ禍での新たな働き方が求められる中で、導入を検討する企業が増えています。
サテライトオフィスが必要とされる理由
サテライトオフィスは、少子高齢化社会において育児や介護と仕事を両立させるための有用な手段であり、地方の活性化や雇用創出など日本の抱える難しい課題を解決できる選択肢の一つです。所属するオフィスを離れ、遠隔勤務用のオフィスで仕事をする働き方は、企業にとっても生産性の向上や離職防止などメリットがあります。
支社・支店との違い
本社とは別の場所に設置されるサテライトオフィスですが、支社(支店)との違いは何でしょうか。
支社は近隣にある取引先の数や物流拠点としての機能など、経営における利点を設置の主な目的としています。そこには所属する従業員がいて、多くは本社とは別の組織や業務を運営する拠点となるのです。
一方、サテライトオフィスは従業員の働きやすさを主な目的としています。一時的な利用になることも踏まえて、企業の多くは従業員が通勤しやすい拠点に通信環境および必要最低限の設備やスペースを確保し、設ける点が特徴です。
リモートワーク・テレワークとの違い
リモートワークは「離れた場所で働く」という意味でサテライトオフィスでの勤務を包括した概念です。一方、テレワークはICT(情報通信技術)を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方を指しており、在宅勤務・(移動中や出先で働く)モバイル勤務・サテライトオフィス勤務が該当します。
つまり、「違い」というよりはサテライトオフィス勤務自体がリモートワークやテレワークの一種なのです。
小規模とはいえオフィスの機能を果たすサテライトオフィスは、在宅勤務やモバイル勤務と比べて仕事に集中できる環境であると言えます。また、一時的なプロジェクトを行う拠点として人が集まって作業できるという点も、サテライトオフィスの特徴です。
その他のオフィス形態
サテライトオフィスには自社専用と他社共用の2種類があります。自社専用で使用する場合は社内LANが利用できるためセキュリティ面での心配が少なく、社内の従業員同士で情報共有や交流できる点がメリットです。
他社共用のサテライトオフィスはシェアオフィスやコワーキングスペースとも呼ばれます。起業家・フリーランス・個人事業主などが貸主と契約する形式なので、通いやすい場所を見つけて気軽に利用できますが、セキュリティーやプライバシーの確保には注意が必要です。
サテライトオフィス4つの種類とは
サテライトオフィスには都市型・郊外型・地方型・自治体運営型の4種類があります。それぞれのサテライトオフィスの特徴を押さえながら、企業の場所や目的に適したタイプを検討してみましょう。
都市型
都市型サテライトオフィスの設置目的は主に2つです。1つ目は、地方に本社のある企業が都市部に営業所としてサテライトオフィスを設置する場合です。この場合、都市部で営業活動や情報収集をしながら地方企業の業務に貢献できます。
2つ目は、都市部に本社がある企業が同じ都市部に第2、第3営業所のような形でオフィスを設ける場合です。この場合、営業担当者が営業先(または自宅)に近いサテライトオフィスに戻って仕事を続けることで、移動のコストと時間を減らし業務を効率化できます。
郊外型
郊外型サテライトオフィスは、都市部にある本社への通勤にかかる時間と費用を削減し、従業員のワークライフバランスを整えることが主な目的です。
1日あたり往復の通勤時間が平均1時間半と言われる都市部において、郊外のベッドタウン近辺にオフィスを置くことは、育児や介護との両立やプライベート時間が確保できる点でメリットがあります。また、企業側にとっても上記の理由から社員の離職を防ぐ施策として期待できるでしょう。
地方型
地方型サテライトオフィスの主な設置目的は、BCP(事業継続)対策と地方の雇用の促進です。本社が都市部にある企業が地方に事業のバックアップ機能を備えることにより、自然災害に被災した場合などに受けるリスクを軽減することができます。
また、地方におけるビジネスの活性化や地方の優秀な人材の活用が見込まれるため、地方へのIターン・Uターン希望者にも適した環境を提供することができます。
自治体運営型
自治体運営型とは民間ではなく自治体が運営しているサテライトオフィスです。例えば、東京都では東京テレワーク推進センターが、都内3ヶ所で「TOKYOテレワーク・モデルオフィス」という名称のサテライトオフィスを運営しています。
また、地域での新しい働き方や仕事を生み出す施策として、総務省でも「おためしサテライトオフィス事業」などの支援事業が実施されており、自治体からも多様な働き方への支援が広がっています。
サテライトオフィスを持つ5つのメリット
では、ここからはサテライトオフィスを設置するメリットを5つの視点から解説していきます。
生産性の向上とコスト削減
サテライトオフィスの導入により、自宅からの通勤時間や営業先からの移動時間が短くなると、移動にかかるストレスは緩和され、業務時間にゆとりが生まれるため生産性の向上が期待できます。通勤・移動時の混雑からくるストレスの減少や、時間へのゆとりから生まれるワークライフバランスの向上も、長期的な目線で見て仕事への意欲につながるでしょう。
また、従業員の交通費を削減できる点に加えて、簡易的にオフィスを構えられるサテライトオフィスでは固定経費の削減が可能となり、その余剰資金を人材の確保や設備投資に活かすこともできます。
介護や育児による離職防止
家族の構成によっては、親の介護や子どもの病気等を理由に遅刻や早退の急な対応を余儀なくされる場合が多くあります。豊富な経験や働くモチベーションがあるにもかかわらず、介護や育児を理由に退職することは、従業員にとっても企業にとっても大きな損失です。
サテライトオフィスの設置は、働き続けやすい職場環境を提供することにより離職防止対策になるだけでなく、様々な制約から仕事を継続できなかった人にも社会復帰できる可能性が広がります。
地方創生と優秀な人材確保
地方型サテライトオフィスを設置すると、地方活性化への貢献と優秀な人材の確保が可能です。地方に新たな拠点を設け地域活性化に寄与することは、一企業として地域発展および日本社会全体に貢献することとなります。
そして労働人口の減少が止まらない今、企業にとって人材確保は重要課題です。地方での採用活動の実施により、都市部への通勤を希望しない優秀な人材や、地元や地方での就職を希望する人を活用することが可能となり、さらなる地方創生の一助ともなるのです。
災害時のリスク回避と事業計画継続
サテライトオフィスは、有事や災害に関連する場面でのBCP対策に役立ちます。BCPとは、自然災害等の緊急事態に直面した場合に、事業を継続または素早く復旧するための計画のことです。
例えば、一拠点しかないオフィスに重要なデータが集約されていた場合、災害等でデータが消失し機能不全を起こすことで業務が滞ってしまいます。さらにこのような事例においては、被災前の営業可能な環境が整うまで、多くの時間を要する可能性があります。
サテライトオフィスにて本社機能を引き継ぐ準備をしてリスク分散しておけば、予期せぬ災害に遭っても拠点を移して事業を続けていくことが可能になるでしょう。
企業のブランド力が上がる
国を挙げて「働き方改革」に取り組んでいる今、サテライトオフィスを積極的に導入し、運用を成功させた実績を持てば、時代に即した企業として認知されます。上手く活用すれば従業員の働きやすさが向上し、企業のイメージアップにもつながるでしょう。
転職や就職で「自分らしい」働き方を重視する現代社会においても、好意的に受け止められるものとなります。
紹介した様々なメリットを通して、サテライトオフィスを設置する意義を感じてもらえたのではないでしょうか。
サテライトオフィスの設置を成功に導く4つの注意点と解消法
では、実際にサテライトオフィスを設置する際に気を付けるべき点とはどのようなものでしょうか。以下の項目を抑えておくことで、サテライトオフィスの運営を失敗なくスムーズに始めることができます。
社員管理と評価方法を検討する
サテライトオフィスでは管理者と離れて勤務するため、従来の勤怠管理制度では人事評価が難しくなる可能性があります。評価の仕方として、例えば勤務状況と内容をまとめたレポートを提出する、といった方法がありますが、それでは仕事の成果や結果しか見ることができません。
勤務時間、業務内容、相談ごとなどを遠隔でもスムーズに共有するためには、適したICTツールの導入を併用し、気軽にコミュニケーションを図れる環境に整える必要があります。また、導入前から従業員の自己管理意識を高める意識づけをすることも、生産性の低下を防ぐために重要と言えるでしょう。
コミュニケーションロスを起こさない仕組みを作る
先述のとおり、管理者や従業員同士の物理的な距離により円滑なコミュニケーションが取れない場合、従業員の困り事に気づくことができなければ、業務に支障が出かねません。
まずはZoomなど顔の見える会議ツールや、Slackといったビジネスに適したチャットツールを利用して、相手の状況を確認しながら情報を共有してみましょう。相手の顔と声を知り、気軽に文章を送りあえる関係性から、互いに声をかけやすい体制を作ることが大切です。
とはいえ、ICTツールで環境を整えていてもオンライン上のコミュニケーションだけでは孤独を感じやすいものです。サテライトオフィスを利用する社員には、こまめな連絡や明快な説明を心掛け、定期的に対面する機会を持つなどの工夫も取り入れてみましょう。
セキュリティを保つための工夫をする
特に他社と共用するタイプのサテライトオフィスではセキュリティ対策が必須です。機密文書や社内情報の取り扱いへの明確なルールを整備した上で、従業員のセキュリティに対する判断能力を定期的に確認する必要があります。
自社以外のサテライトオフィスで使用するIT機器は、必要以上の情報を保管しないようまずパソコン内を整理します。セキュリティソフトをインストールし、セキュリティロックや覗き見防止フィルターなどを使って情報漏洩に対する防止策を講じましょう。
web会議や商談の話し声からの情報漏洩が心配な場合は、防音のワークブースを備えたサテライトオフィスがお薦めです。セキュリティ対策を万全にしておけば、サテライトオフィスの設置をより安心して進められます。
拠点間の格差が起こらないよう配慮する
特に本社が都心にある郊外型・地方型のサテライトオフィスでは、研修やセミナーへの参加が難しく、拠点間でインプットできる情報に格差が生じることがあります。
しかし、コロナ禍を経てオンライン上で受けられるセミナーの数は急増し、従業員がオンライン上でセミナーに参加する抵抗感は薄くなっています。企業側は拠点間での環境の差をしっかりと把握した上で、適切な機会を提供することで拠点間の溝を最小限に抑えられるでしょう。
地方自治体からの助成や支援について
サテライトオフィスを検討する際、国や地方自治体からの助成や支援を受けられる場合があります。以下を参考に該当する自治体にも支援があるか確認してみましょう。
◆総務省・厚生労働省「テレワーク助成金」
良質なテレワーク制度を導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等で効果をあげた中小企業事業主を支援する助成金です。テレワーク用通信機器の導入や労働者に対する研修等が要件となっている「機器等導入助成」と、離職率の低下やテレワークを実施した労働者の数を要件とする「目標達成助成」があります。
詳細はこちらをご確認ください。
引用:総務省・厚生労働省
https://telework.mhlw.go.jp/support/subcidy/
◆公益財団法人の東京しごと財団(東京都)「サテライトオフィス設置等補助事業」
東京都内において通勤時間の削減や家庭と仕事の両立を目的とした職住近接の働き方を推進する事業です。都内でも施設の設置が少ない市町村部において、共用型サテライトオフィスを新たに開設する際の整備や運営費用の補助を行っています。
コース・補助要件・補助額等の詳細はこちらをご確認ください。
引用:公益財団法人東京しごと財団
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/satellite.html
まとめ
ここまでサテライトオフィスについて、その種類や設置される背景、補助金制度までを詳しく解説してきました。様々なメリットや注意点を踏まえて準備を進めれば、サテライトオフィスは企業にとっての持続可能な経営と、従業員にとっての柔軟で働きやすい環境の実現を可能にするのではないでしょうか。
サテライトオフィスの設置や利用にあたり、色々なオフィス用品をそろえたいなら法人向けオフィス通販のスマートオフィスをご活用ください。デスク周りで必要な物から盗難防止グッズまで様々なオフィス用品を数多く取り揃えておりますので、是非ご活用ください。
