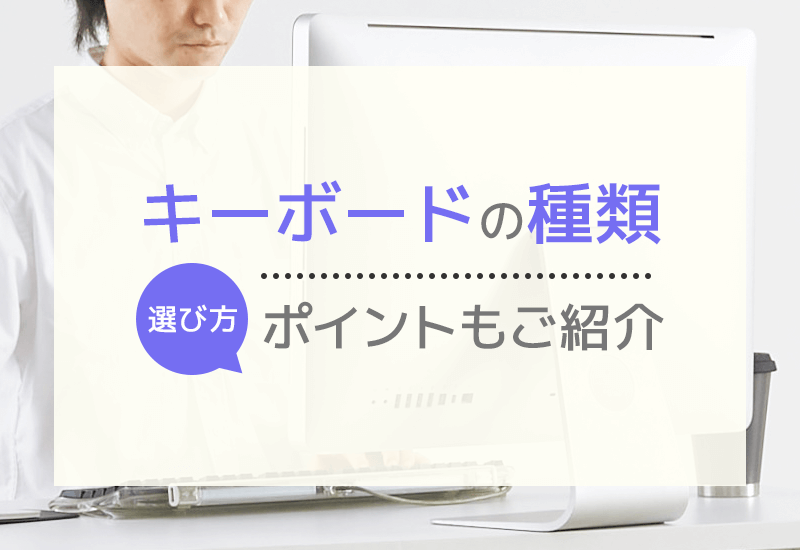
目次
キーボードは、パソコンで作業をする時の必須アイテムです。最近では、デスクトップパソコンだけでなく、タブレット端末やスマートフォンでも、キーボードを接続して利用する人が増えてきました。
しかし、キーボードを購入しようと思っても、あまりの種類の多さに、どれを選べばよいのか分からないという人も多いのではないでしょうか。
このコラムでは、キーボードの種類や特徴、選ぶ際のポイントなどを紹介します。キーボード選びにお困りの方は、ぜひ参考にしてください。
キーボードの主な種類
まず、構造の違いによって分類された「メンブレン式」「パンタグラフ式」「メカニカル式」「静電容量無接点方式」について、それぞれのキーボードの特徴を見ていきましょう。
打鍵感(だけんかん・キーを押した時の手ごたえ)の違いについては、後述の「キーボードを選ぶ際に注目すべきポイント」の中で説明していますので、そちらを参考にしてください。
メンブレン式キーボード
メンブレン式キーボードは、デスクトップ用のキーボードによく使われるタイプで、キーを押すと、2枚のシートが接触して入力を認識します。キーの下にラバーカップというパーツがあり、キーを戻す時には、ゴムの反発力を利用する仕組みです。
部品の数も少なく、センサー部分にゴムを使っているため、安価で入力時の音が静かなのが特徴です。
ただし、ゴムの劣化によって打ちづらくなってしまったり、キーの中央を押さないと正しく入力されなかったりするというデメリットがあります。
パンタグラフ式キーボード
パンタグラフ式キーボードは、薄型キーボードによく使われるタイプで、ノートパソコンに多く採用されています。基本的な仕組みはメンブレン式と同様ですが、X字型の軸をキーの支持構造に使用したことで、キーの中央以外を押した時も入力をしっかり認識できます。軽いキータッチで入力が可能なのが特徴です。
薄いので持ち運びにも便利ですが、耐久性に劣るというデメリットがあります。
メカニカル式キーボード
メカニカル式キーボードは、すべてのキーに機械式のスイッチとスプリングが配置されています。スプリングを使用しているためキーの動きがなめらかで、カチカチというタイピング音も特徴的です。
それぞれのキーが独立して動作するので、ゲームなどで複数のキーを同時に押すことに適しています。カスタマイズ性が高いのもメカニカル式の魅力の一つですが、構造が複雑なため、高価なものが多い点がデメリットです。
静電容量無接点方式キーボード
静電容量無接点方式キーボードは、入力の際の物理的な接点を持たず、静電気を感知して入力します。パーツ同士が接触しないので、タイピング音も静かで、摩耗しにくく耐久性にも優れています。
また、チャタリング(誤って二重入力してしまう現象)が発生せず、高速入力にも最適です。デメリットは、性能の高さゆえに高価であることと、薄いタイプのものがないことです。
キーボードを選ぶ際に注目すべきポイント
キーボードを選ぶ際には、どのような点に注目して選べばよいのでしょうか。使用場所や使用目的などによっても、さまざまなポイントがあるので、順番に解説します。
打鍵感で選ぶ
キーボードを選ぶ際、打鍵感の好みは大切な要素の一つです。ここでは、先述の4種類のキーボードについて、打鍵感の特徴とどのような人にお薦めなのかを紹介します。
メンブレン式
ゴムを使用しているため、やわらかい打鍵感が特徴ですが、爽快さには欠けます。キーをしっかりと押さなければならないので、指が疲れやすく長時間の使用にはあまり適していません。
とにかく安く購入したいという場合や、使用時間が短いという人にお薦めです。
パンタグラフ式
深く押さなくてもキーが動作するので、高速でのタイピングが可能です。静かで軽い打鍵感は魅力でもありますが、人によっては物足りなさを感じるかもしれません。
少ない力で入力できるので、疲れにくく、長時間使用したい人にはお薦めです。
メカニカル式
爽快感のある心地よい打鍵感が特徴です。ただし、スプリングの種類によっても打鍵感は異なるため、好みに応じて選ぶとよいでしょう。
ゲーム用のキーボードとして使われることが多いですが、作業用としても人気です。
静電容量無接点方式
パーツ同士が接触することがないので、打鍵感は軽くてとてもなめらかです。キーを押す時の引っかかりがなく、底まで押し込む必要もありません。
高価ですが、静音性・耐久性が高く、タイピング疲れもしにくいため、仕事などで長時間使用する人には最適です。
接続方式で選ぶ
接続方式は、大きく分けると「ワイヤレス(無線)方式」と「有線方式」の2つに分けられます。それぞれメリットとデメリットがあるので、用途に応じて使いやすい方を選択するようにしましょう。
ワイヤレス方式
ワイヤレス方式には、「Bluetooth接続」と「USBレシーバー接続」のキーボードがあります。ワイヤレス方式のメリットは、通信できる範囲ならどこからでも使用が可能なことと、ケーブルが不要なので、デスク周りがすっきりすることです。
デメリットとしては、入力時のレスポンスに遅延が生じてしまったり、電波障害などで正確に入力できなかったりする場合があることが挙げられます。また、キーボードの電池切れやバッテリー切れにも注意が必要です。ワイヤレスキーボードを選ぶ際は、連続稼働時間も確認して選ぶようにしましょう。
有線方式
有線方式では、キーボードとパソコンやタブレット端末を、直接USBケーブルで接続して使用します。メリットは接続が安定していて、反応速度が速いことです。ペアリングなどの作業も不要ですぐに使い始めることができ、電池やバッテリー切れの心配もありません。
デメリットは、接続用のケーブルが必要になり、そのケーブルでデスク周りが煩雑になりやすいことです。また、ケーブルが届く範囲でしかキーボードを使用できないので、使用範囲を考えて選ぶ必要があります。
テンキーの有無で選ぶ
テンキーとは、0〜9の数字と計算記号のキーをまとめたもので、主にキーボードの右側に配置されます。このテンキーの有無も、キーボードを選ぶ際の基準になります。
テンキー有り
数字を入力したり、計算したりすることが多い場合は、テンキーがあった方が入力効率が上がるので、テンキーの付いたキーボードがお薦めです。
ただし、キーボードの横幅は、テンキー無しのモデルに比べて10cm程度大きくなってしまうので、その点は注意が必要です。
テンキー無し
数字を入力する機会が多くない場合は、テンキー無しのキーボードの方が、コンパクトでお薦めです。テンキーがなくても数字の入力は可能なので、数字の使用頻度が高くない場合は、こちらを選ぶとよいでしょう。
配列で選ぶ
キーの配列は、キーボードによって少しずつ異なります。使っているうちに慣れてくることもありますが、使い慣れているものや、違和感の少ないものを選ぶとよいでしょう。
ここでは、よく使われる「日本語配列」と「英語配列」の違いを説明します。
日本語配列
日本語配列のキーボードの特徴は、「変換」や「半角/全角」、「カタカナ/ひらがな」といったキーが配置されていることと、Enterキーが大きめで押しやすくなっていることです。
日本語の入力では、漢字などに変換して、Enterキーで確定することが多いので、これらの特徴によりスムーズな入力が可能になります。
ただ、キーキャップにアルファベットとひらがなが両方印字されているので、少し煩雑な印象があるかもしれません。
英語配列
英語配列のキーボードは、単語間にスペースを入れることの多い英語入力に対応するため、スペースキーが大きくなっています。英語の文章を入力することが多い人には、こちらがお薦めです。
キーキャップの印字は日本語配列と比べて少なく、すっきりとした印象です。
打ちやすさで選ぶ
キーボードを選ぶ際、打ちやすさは非常に重要です。打ちやすさを大きく左右するのは「キーストローク」と「キーピッチ」だといわれています。それぞれ解説します。
キーストローク
キーストロークとは、キーを押した時に沈みこむ深さのことで、デスクトップパソコンでは3~4mmが一般的です。
キーストロークが深いと、しっかり押し込む必要があり、誤入力が起きにくくなります。その反面、入力速度は遅くなるので、速さを求めるなら、キーストロークが浅いものの方がよいでしょう。
キーピッチ
キーピッチとは、隣り合うキーの中心間の距離を指し、19mm程度が一般的です。
キーピッチが広めの方がタイピングはしやすいので、19mmを基準にして判断するとよいでしょう。持ち運びやすいコンパクトなキーボードは、キーピッチが狭い場合があるため、操作性を確認することも大切です。
軸の違いで選ぶ
メカニカル式キーボードを選ぶ場合には、「軸」の種類も確認するようにしましょう。「軸」とは、キーキャップを取り外した時に見えるキースイッチのことです。このキースイッチの色によって、以下のような特徴があります。
赤
赤軸は、なめらかな打ち心地で、最も人気のある軸です。少ない力で入力できるので、長時間タイピングする人に向いています。静音性にも優れていますが、それでもタイピング音が気になる場合は、より静音性の高い、ピンク軸(静音赤軸)を検討してみてください。
青
青軸は、最も打鍵感が強いキーボードです。押し方の強さに関係なく「カチッ」という大きなタイピング音が響き、しっかりした打鍵感が得られます。爽快感のある打ち心地が魅力ですが、音が大きいので、周りへの配慮が必要です。
茶
茶軸は、平均的でクセがないタイプなので、初心者にもお薦めです。打鍵感やタイピング音も、赤軸と青軸の中間程度で、スタンダードな性能を持つ軸です。あまりこだわりがないという人は、茶軸を検討してみるとよいでしょう。
銀
銀軸は、スピード軸とも呼ばれ、素早いキー操作にも反応が可能です。そのため、ゲーミングキーボードにも採用されています。キーストロークが浅いので操作もしやすく、入力速度にこだわりたい人に向いています。
黒
黒軸は、キーを押すために必要な力が他の軸よりも重く、キーを押し込む感覚が味わえます。長時間の作業にはあまり向きませんが、しっかりした打鍵感は、入力ミスを軽減してくれるでしょう。静音性にも比較的優れています。
使用目的で選ぶ
キーボードを選ぶ際には、打ちやすさの好みなどの他、使用目的に応じて選ぶことも重要です。仕事用なのかゲーム用なのかによっても、最適なキーボードのタイプは異なります。ここまで紹介してきたキーボードの特徴が、自分の使用目的にあうか考えて選ぶようにしましょう。
まとめ
作業効率を上げるためにも、キーボードを選ぶ際は、自分の好みや使用目的、それぞれのキーボードの特徴を理解して選ぶ必要があります。
このコラムでも、キーボードの種類や選び方のポイントをいろいろと紹介してきましたが、実際に選ぶとなると、迷ってしまう人が多いのではないでしょうか。数あるキーボードの中から、自分にあったキーボードを見つけるのは、至難のワザです。
キーボード選びにお困りの場合は、法人向けオフィス通販サイト「スマートオフィス」の利用がお薦めです。スマートオフィスなら、キーボードの品揃えも豊富で、購買のサポート体制も整っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。
