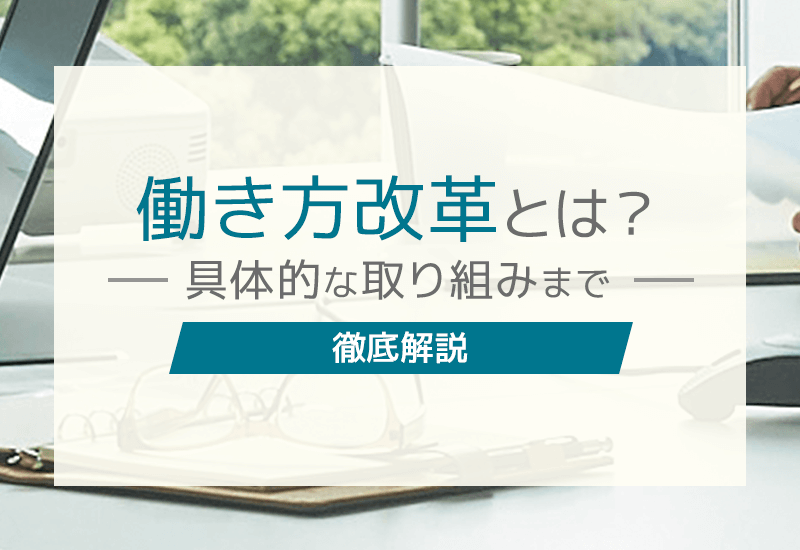
目次
一億総活躍社会の実現に向け、政府主導で進められてきた「働き方改革」。労働者のさまざまな事情に関わらず、働くことを自身で選択できる社会の実現を目指しています。
雇用側も従業員が中長期的に活躍できる環境を整備することによって、労働力を確保できるというメリットがあります。しかし、そもそも「働き方改革って何?」「企業として何をすれば良いの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
本コラムでは、政府の取り組み内容をはじめ、企業で取り組みできる事例について具体例を挙げつつ解説いたします。
働き方改革とは?3つの柱を解説
そもそも働き方改革とは「少子高齢化による労働人口の減少」や「働き方の多様化」などに対応し、労働力を確保することを目的としています。
2019年に施行された働き方改革関連法案では、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現することを目的に、3つの柱を掲げています。具体的にご紹介しましょう。
長時間労働の是正
働き方改革では、企業に対して長時間労働の改善が求められています。具体的には、休日稼働や残業時間を減らすといった対応です。
この政府の呼びかけの背景には、日本の長時間労働による過労死の増加が影響しています。実は2013年頃から日本は国連からこの問題に対する是正勧告を受けていました。世界的に見ても日本の働き過ぎは深刻な問題だったことから、政府が働き方の是正に着手し始めたのです。
そもそも使用者である企業は、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて労働させるために、労働者と企業間で36協定という労使協定を締結する必要があります。しかし、2018年度の法改正により時間外労働の上限が月45時間、年360時間に定められました。企業として可能な限りこの水準に近づけることが求められています。
多様で柔軟な働き方の実現
中長期的な労働力の確保において、従業員が多様な働き方を選択できることは非常に重要です。
例えば、テレワークやフレックスタイム制度は、子育て世帯や介護をしながら働いている人には大変助かる制度の一つです。従業員の生活環境の変化に対して柔軟に対応できる環境の整備は、中長期的に活躍してくれる従業員の確保には欠かせません。
最近は、ワークライフバランスを重視する人も増えているので、ぜひ積極的に検討しましょう。
雇用形態にかかわらない待遇の保持
有期雇用やパートタイムの従業員と、正社員との待遇の差を埋める取り組みです。日本は諸外国から見ても、正社員と契約社員の給与水準の差が大きいと言われています。
そのため、有期雇用やパートタイムの従業員と正社員との給与水準が大きく異なる場合は、それぞれの仕事内容や職能を洗い出し、なぜその差が生じるのかを明確にしなければなりません。もし同じ業務を行っているのであれば、待遇は統一する必要があるでしょう。
働き方改革によるメリット
企業の存続において、利益を生むことは重要です。しかし、長時間労働で「従業員が病気になってしまった」といった事態はなんとしても避ける必要があります。
無理な働き方を続けることは、従業員にとっても企業にとってもメリットがありません。ここでは働き方改革の導入による、企業側と従業員側それぞれのメリットについて解説します。
企業側のメリット
働き方改革による最大のメリットは、中長期的な労働力の確保です。少子高齢化によって売り手市場が続く昨今、働き手の確保は企業の存続において最重要テーマとも言えます。この労働者を確保する方法の一手とも言えるのが、働き方改革です。
また、長時間労働が是正されることによって、短時間で成果を挙げることが求められるため、必然的に生産性向上へと繋がります。
本質的な働き方の改善は、企業として「従業員を大切にする会社」というイメージにも繋がるため、企業の信頼性を高める上でも有効です。
従業員側のメリット
プライベートの時間をしっかり確保することは、心身ともに健康な状態を保つことでもあります。スキルアップや学びの時間を得ることで、働くことへのモチベーションを高めることにも繋がるでしょう。
また、出産・育児・介護といった生活の変化に関わらず、柔軟に働ける仕組みがあれば、収入や生活の安定という面でも安心して働くことができます。スキルや能力があるのに働くことを諦めざるを得なかった人も、活躍する機会が増えるでしょう。
働き方改革が必要とされる背景
現在、日本は少子高齢化による労働力不足をはじめ、ニーズの多様化、雇用形態による待遇の格差といった様々な問題を抱えています。
働き方改革はそのようなニーズに応えるべく、推進されています。本項で具体的な理由や背景をご紹介しましょう。
労働人口の減少
100年後、日本の人口は現在の約1/3まで減少すると予測されています。例えば、2023年1月時点における日本の総人口は1億2,242万人余りと言われているため、2100年頃には4,000万人程にまで落ち込む計算となります。
同様に働き手となる労働人口も2060年頃には4,500万人にまで落ち込むことが予測されているため、日本国としての労働力の減少は確実に近い将来に迫っています。
そのため、政府としても働き方改革を通じ、何とかして生産性向上や労働力確保に努めたいわけです。
多様な働き方へのニーズの高まり
日本で従来は良しとしてきた長時間労働やプライベートを犠牲にするような働き方は、もはや悪しき文化として認識されてきています。
このような価値観やニーズの変化、政府の働き方改革の推進なども手伝って、多様な働き方を求める声が挙がっています。
また、最近は物価の上昇によって、副業をする方も増えています。以前の働き方では生活水準が保てなくなっていることも、背景の一つだと言えるでしょう。
働き方改革の実現に向けた国の取り組み
働き方改革は、日本の雇用における約7割を担う中小企業や小規模事業者において、着実に実施されることが重要だと言われています。
職場環境を改善することで、企業の魅力を向上させ、労働力の確保や生産性の向上へと繋げるためです。それでは日本ではどのような取り組みを行っているのでしょうか。
長時間労働の是正
1947年に制定された「労働基準法」の70年ぶりの改定によって、法律上下記の時間に残業が規制されるようになりました。
残業時間(原則):月45時間・年360時間
法定労働時間:1日8時間・週40時間
雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
正規・非正規といった雇用形態に関わらず、誰もが平等かつ健やかに働ける環境を整える取り組みです。具体的には同じ職務内容にも関わらず、待遇に差があるといった不合理な差があるなどを規制しています。
<判断基準となる規定>
・均衡待遇規定…不合理な待遇差の禁止
・均等待遇規定…差別的取扱いの禁止
柔軟な働き方がしやすい環境整備
これまではオフィスに出社して働くことが当たり前でしたが、テレワークなどの導入によって離れた場所でも働くことができる環境整備が促進されています。
また、フレックスタイム制も清算期間が1か月から3か月に拡大されました。3ヵ月間という期間の中で、労働時間が調整できるため、より柔軟な働き方が実現できます。
ダイバーシティの推進
ダイバーシティとは多様性を意味します。政府は、性別や年齢、人種や国籍、宗教、障がいの有無、性的志向などに関わらず、それぞれの能力が発揮できる機会を与えることを推進しています。
賃金引き上げ・労働生産性向上
月間60時間を超過する労働に対して、これまでは大企業が50%、中小企業が25%割増賃金率が定められていました。法改正によって、2023年度に中小企業も50%へと引き上げられました。
再就職支援・人材育成
働き方やニーズの多様化によって、企業や労働者双方で再就職への需要が高まっています。そのため、年齢に関わりのない適正な評価や採用、採用後に活躍するための人材育成に対する取り組みが促進されています。
ハラスメント防止対策
2019年度に女性活躍に向けて「労働施策総合推進法」の一部が改正され、男女の雇用機会均等法や育児・介護休業といった内容も整備されました。この改正によって、企業は職場におけるパワーハラスメントの防止やコンプライアンスの設定が義務化されました。
企業が実践する働き方改革の主な取り組み6選
日本の労働環境は、長年にわたって課題が山積みでした。今回ご紹介している働き方改革は、従業員が働きやすい環境を整えるだけでなく、生産性の向上によって企業側にもメリットがあるものです。実際に企業が実践する取り組み内容を6つご紹介します。
テレワークの推進
テレワークはオフィスに出勤せず、自宅に居ながら働くことができるため「通勤による負担軽減」や「時間の有効活用」といった生産性の向上が期待できます。
また、育児や介護といった事情を抱える優秀な人材が、通勤を理由に離職することを防ぐ効果も期待できるでしょう。
非正規雇用者の待遇を正規雇用と同水準まで上げる
政府の働き方改革の一つとして、正規・非正規に関わらず同一の仕事をしていれば、同一の賃金を支給する考え方である「同一労働・同一賃金の原則」が2020年4月から適用されました。
この規定では、賃金だけでなく研修制度や福利厚生といった内容も改善すべき対象として挙げられています。不合理な待遇の差を無くすことは、働く人のモチベーションを高めることに繋がります。
企業側はこのような格差を減らし、より良い労働環境を整えなければなりません。
フレックスタイム制度の導入
フレックスタイム制とは、労働者に始業時間と就業時間の裁量が与えられる制度です。従業員は、出産・育児・介護といったライフイベントの際にも、仕事とプライベートのバランスを実現できます。
仕事の効率化だけでなく、離職率を低下させたり採用時のアピールポイントになったりもします。
残業時間に上限を設ける
長時間労働を無くすためには、残業時間に上限を設定することが効果的です。働き方改革によって定められている時間外労働は原則として月45時間、年360時間までとされています。
ツールなどで勤務時間を見える化することによって、従業員も許容される残業時間の残りを確認しやすくなります。
育児休暇の取得を促進する
育児休暇は女性だけでなく、男性も取得しやすい環境を整える必要があります。夫婦で協力しながら子育てできる環境づくりをサポートできる点も、メリットの一つです。どちらかが子育てを背負い、離職せざるを得ないといった状況になるのを防ぐことにもなるでしょう。
有給休暇の取得率を上げる
労働基準法が改正されたことで、年次有給休暇の取得が義務化されました。従業員が有給を消化できない場合、企業には罰金が科せられる可能性があるので、企業には有給休暇を取得しやすい環境づくりが求められます。
建設業や物流・運送業などの「2024年問題」とは?
政府が取り組む働き方改革において、いま大きな問題となっているのが2024年問題です。
2024年問題とは、2024年4月に適用が開始される働き方改革関連法によって、物流や運送業界、建設業界といった業界が影響を受ける問題の総称です。
一見すると、企業・従業員双方にメリットが多そうな取り組みですが、諸問題の発生が懸念されています。その一つが物流の停滞です。
例えば、時間外労働の上限である年960時間は、目安として1か月で約80時間となります。しかし、トラックドライバーは1カ月の時間外労働が275時間以上だと言われています。
そのため、時間外労働を274時間以下に収めようとすると物流の停滞や業界全体の利益減少、ドライバーの収入減少などが予測されています。企業はこれまでの働き方を見直して改善するとともに、このように懸念される問題にも対応しなければなりません。
まとめ
日本全体が取り組むべき問題ともいえる働き方改革。特に、生産性の向上においては、商品やサービスによるサポートも必要です。
「自社の働く環境を改善したいと思っているが、なかなか準備が進まない」と頭を抱えているようであれば、相談しながら購入ができる法人向けオフィス用品通販スマートオフィスをお薦めします。
自社の課題やニーズに応じて、担当営業が各お客様に合わせた商品や買い方をご提案します。中長期的に自社の魅力を高め、労働力を確保するためにも取り組んでおきましょう。
